自分の強みを伸ばすコーチング入門|失敗しない実践ステップと活用事例集

「自分の強みを活かして生きたい」と思っても、具体的にどう見つけ、どう伸ばせばいいのか迷う人は少なくありません。そこで注目されているのが「コーチング」です。コーチングは一方的な指導ではなく、問いかけや対話を通じて本人の内面にある答えを引き出す手法。
この記事では、強みとコーチングの関係、活かし方のステップ、成功事例、注意点までを徹底的に解説していきます。
強みとは何か?コーチングで扱う「強み」の定義

強みという言葉は日常的に使われますが、コーチングの文脈では少し特別な意味を持ちます。一般的に「得意なこと」や「スキル」を指すことが多いですが、コーチングでいう強みは「その人の中に自然と存在している才能や資質」を意味します。
例えば、以下のようなものです。
- 人の話を最後まで聞ける忍耐力
- 新しいアイデアを生み出す創造力
- 難しい状況でも前向きに捉える楽観性
- 相手の気持ちに寄り添う共感力
これらは、訓練や勉強だけでは得られない「自然体で発揮できる特性」です。
ポイント
- 強み=スキルではなく「資質」
- 自然体で繰り返し発揮される行動パターン
- 他者から「あなたらしいね」と言われる部分にヒントがある
注意点
- 苦手を克服する方向ばかりに目を向けると強みを見失いやすい
- 短所の裏返しが強みになるケースも多い(例:頑固⇔信念が強い)
強みは「自然に繰り返し現れる資質」として捉えられますが、同時に他者との関わりで磨かれていく特徴も持ちます。人は自分では気づけない部分を他人の反応によって認識することがあります。つまり、強みは自己と他者の対話の中で育まれる動的なものです。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
なぜ強みを知ることが大切なのか

強みを理解することは、自己理解の基盤となります。なぜなら、人は「強みを発揮できる環境」で最も力を発揮するからです。
強みを知るメリット
- 自分らしいキャリア選択ができる
- 自信やエフィカシー(自己効力感)が高まる
- 人間関係の中で役割を見つけやすい
- 成功体験を積みやすくなる
事例
Aさん(30代・会社員)は、自分に強みがないと感じ転職を繰り返していました。コーチングを通じて「人を励ます力」が強みであると気づき、その後は人材育成に関わる部署に配属。成果を上げ、自己肯定感も回復しました。
強みを理解した人と理解していない人の違い
| 項目 | 強みを理解していない人 | 強みを理解している人 |
|---|---|---|
| キャリア選択 | 他人の評価に流される | 自分に合った選択をする |
| 自信 | 低く揺らぎやすい | 高く安定しやすい |
| 人間関係 | 無理に合わせて疲れる | 自然に役割を発揮できる |
| 成長速度 | 遅く停滞しやすい | 加速して成果を得やすい |
強みを理解することは「自分らしい選択」を可能にします。苦手を克服する努力だけに偏ると心身が疲弊しますが、強みを軸にすれば努力が成果につながりやすいのです。また、強みを認識している人は挑戦にも前向きで、挫折からの回復も早い傾向があります。
強みを引き出すコーチングの基本プロセス

コーチングでは「質問」と「傾聴」を通じて、本人の中に眠っている強みを引き出します。基本の流れは以下の通りです。
ステップ
- 自己理解を深める質問
例:「子どもの頃から夢中になれたことは?」「人からよく頼まれることは?」 - 強みの言語化
漠然とした得意分野を「共感力」「挑戦心」といった言葉で表す - 強みの活用場面を探す
仕事・プライベートで強みを活かせる状況を整理 - 行動計画を立てる
強みを発揮する具体的行動を決める
事例
Bさん(20代・新入社員)は、自己評価が低く「特に得意なことがない」と思っていました。コーチングで「人に質問をする力」が強みと判明。営業活動に応用すると、顧客の信頼を得て契約率が向上しました。
注意点
- 強み探しに時間をかけすぎると「完璧な答え」を求めて動けなくなる
- 強みは固定されたものではなく「育つ」ものである
コーチングでは質問と傾聴を重ねることで、本人が「自分の中に答えを持っている」と気づけるように促します。強みを引き出す過程は一度きりではなく、対話を繰り返すことで精度が高まっていきます。状況や経験に応じて強みの意味も変化する点が重要です。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
代表的なフレームワークとツール(ストレングスファインダーなど)
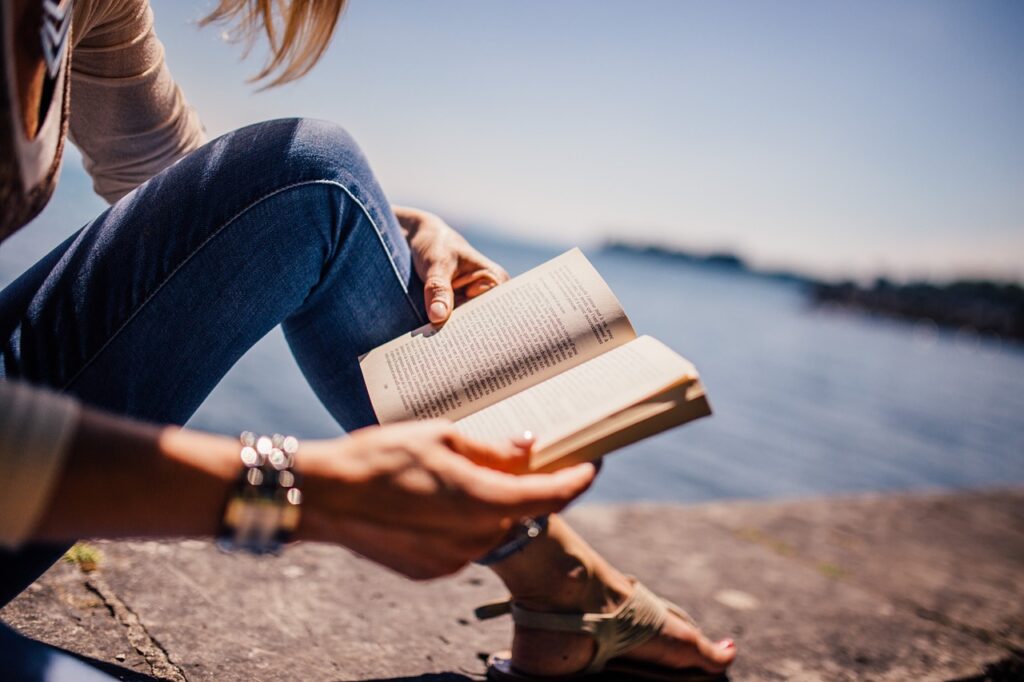
強みを知る方法はいくつも存在しますが、その中でも広く使われているのが「フレームワーク」や「診断ツール」です。コーチングでは、こうしたツールを補助的に活用し、本人の内面と対話を深める材料にします。
代表的なツール
- ストレングスファインダー
米国Gallup社が開発。34の資質から上位5つの強みを特定。
例:「着想」「調和性」「責任感」など。 - エニアグラム
9つの性格タイプをベースに、強み・弱みのパターンを把握。
「改革する人」「助ける人」「挑戦する人」など。 - 16Personalities(MBTIベース)
外向・内向、直感・感覚など4指標を組み合わせた16分類。
性格の傾向を可視化し、強みの理解に役立つ。 - 自己レビュー法
過去の経験を書き出し、「達成できた理由」「楽しかった瞬間」を分析。
診断ツールがなくても実施可能。
ポイント
- ツールは「答え」ではなく「ヒント」をくれるもの
- 出てきた結果を鵜呑みにせず、コーチと一緒に解釈することが重要
注意点
- 結果がネガティブに感じられる場合もある(例:「慎重さ」が裏返って「臆病」と感じる)
- 一度の診断で一生決まるわけではなく、環境や経験で変化する
診断ツールは「自分では見えない一面」を言語化してくれる補助輪のような役割です。ただし、ツールの結果を絶対視せず「今の自分をどう活かすか」を考えるきっかけにすることが大切です。結果を周囲と共有することで、人間関係にも良い影響を与えます。
強みを活かした成功事例
実際に「強み」を発見し、コーチングを通して活用した人の事例を紹介します。
事例1:人材育成に活かしたケース
30代女性Cさんは、職場で「指示待ち」と言われることに悩んでいました。コーチングで「人の気持ちを察する力」が強みだと気づき、後輩指導に活かした結果、チームの雰囲気が改善。上司からも信頼を得て昇進につながりました。
事例2:営業成績が向上したケース
20代男性Dさんは、自分に営業の才能がないと思っていました。しかし、コーチングで「質問力の高さ」が強みであるとわかり、ヒアリングを重視した営業スタイルに切り替え。半年で成績が社内トップに。
事例3:プライベートでの変化
40代女性Eさんは、家庭で「自分には役割がない」と感じていました。コーチングで「計画力」が強みと判明。旅行の企画や家計管理を担うようになり、家族から感謝されるように。
強み活用による変化
| 項目 | Before | After |
|---|---|---|
| 自己評価 | 低い、自信がない | 自信が高まり積極的に行動 |
| 職場での役割 | 受け身・不明確 | 役割が明確化し評価UP |
| 人間関係 | 摩擦や孤立感 | 信頼関係が深まる |
| 成果 | 伸び悩み | 実績や成功体験が増える |
成功事例は「他人の物語」であると同時に、自分へのヒントにもなります。同じ状況ではなくても、強みをどう活かしたかのプロセスは応用可能です。事例を自分の文脈に当てはめて考えることで、行動の選択肢を増やすことができます。
強みが発揮されにくいときの原因と対処法

強みを知っていても、必ずしも常に発揮できるとは限りません。環境や心理的要因によって、強みが「眠ったまま」になってしまうことがあります。
主な原因
- 環境要因
職場や人間関係が強みを活かせる場になっていない。
例:協調性が強みなのに、競争が激しい部署に配属。 - 自己認識の不足
強みを意識していないため、自然と使えていることに気づかない。 - 信念・思い込み
「自分には価値がない」「周囲に迷惑をかけてはいけない」といった信念が邪魔をする。 - 過剰な使い方
強みを使いすぎて逆効果になる。
例:共感力が強すぎて他人の気持ちに振り回される。
対処法
- 環境を見直し、強みを活かせる場を選ぶ
- コーチと一緒に強みを言語化し、自覚的に活用する
- 「短所の裏返し」と捉え、バランスを意識する
- 定期的に振り返りを行い、強みの使い方を調整する
事例
Fさん(20代男性)は「分析力」が強みでしたが、会議で細かく分析しすぎて「話が長い」と言われることに悩んでいました。コーチングで「要点を絞って伝える工夫」を加えると、分析力が活かされつつチーム貢献度も上がりました。
強みを十分に発揮できないのは、自分が未熟だからではなく「環境との不一致」であることも多いです。無理に自分を矯正するのではなく、発揮しやすい環境に身を置くことも立派な選択です。自分の強みを活かせる場を探す視点は非常に重要です。
コーチング実践で役立つ質問例
コーチングにおいて「強みを引き出す質問」は非常に重要です。質問の質が高いほど、相手は自分の中に眠っていた答えに気づきやすくなります。
強み発見のための質問例
- 子どもの頃から自然と得意だったことは何ですか?
- 他人から「あなたにお願いしたい」とよく言われることは何ですか?
- 周囲よりも短時間で成果を出せた経験はありますか?
- 褒められるとしたら、どんな場面ですか?
強み活用を促す質問例
- あなたの強みを活かせる場面は今の仕事にありますか?
- どんな状況なら自然と強みが発揮されますか?
- 強みを今週1回だけ使うとしたら、どんな行動をしますか?
- 自分の強みを他者の役に立てる方法は?
強み育成につなげる質問例
- あなたの強みを10倍にするには、どんな練習が必要だと思いますか?
- 強みを使いすぎて逆効果になった経験は?どう改善できますか?
- 将来のGOALを達成するために、どの強みを伸ばしたいですか?
事例
20代女性Gさんは、自分に特別な強みがないと思っていました。コーチから「他人に自然にしているサポートは?」と聞かれたとき、「友人の相談に乗ること」が浮かびました。そこから共感力と傾聴力が強みとわかり、キャリア支援の分野に進むきっかけとなりました。
質問は相手の思考を整理し、潜在的な強みを表面化させる力を持ちます。具体的かつ未来志向の問いかけは相手を前向きにさせますし、過去の体験を掘り下げる問いは強みを裏付ける根拠を見つけさせます。バランスよく組み合わせることが大切です。
深掘りを促す質問
- 「その行動を自然にできたのはなぜだと思いますか?」
- 「他の人と比べて、自分が得意だと感じる部分はどこですか?」
- 「それをしているとき、時間を忘れる感覚はありましたか?」
こうした質問は、本人が無自覚に繰り返している資質を明確にする効果があります。
行動につなげる質問
- 「その強みを明日一度だけ活用するとしたら、どんな場面がありますか?」
- 「強みをさらに育てるために、今週一つ挑戦できることは何ですか?」
- 「誰にその強みを活かすと、相手が一番喜んでくれると思いますか?」
このように行動に直結する問いを投げると、気づきが具体的な実践へ移行しやすくなります。
ケーススタディ
例えば、ある30代男性は「自分には強みがない」と思い込んでいました。しかしコーチから「周囲に頼られる瞬間はどんなときですか?」と問われ、思い出したのは「職場でトラブルが起きたときに冷静に対応できる」経験でした。そこから「危機管理能力」という強みが浮かび上がり、自信を持って新しいプロジェクトを任されるようになりました。
このように、質問は「強みを見つける」だけでなく「行動のきっかけ」をつくる力があります。質問力を磨くこと自体が、コーチングを効果的にする最も実践的なスキルと言えるでしょう。
注意点とよくある失敗

強みコーチングを実践する際には、いくつかの注意点があります。
よくある失敗
- 強みを固定化してしまう
「自分はこれが強みだから他はしなくていい」と考えるのは危険。
→ 強みはあくまで成長の軸であり、行動の幅を広げる土台。 - 短所を無視する
強みにばかり注目して短所を放置すると、成長が偏る。
→ 弱点を完全に消す必要はないが、最低限の調整は必要。 - 他人の強みと比較してしまう
「自分はリーダーシップがないから劣っている」と思うと逆効果。
→ 強みは人それぞれ。比較よりも「どう活かすか」に意識を向ける。 - 環境に適応させすぎる
「強みを会社に合わせる」ことだけに意識すると、自分らしさを失う。
→ 強みを発揮できる場を選ぶことも重要。
ポイント
- 強みは「唯一無二」であり、人との違いが価値を生む
- 強みは「磨けば育つ」性質を持つ
- 成長には「バランス」と「場の選択」が欠かせない
強み探しに熱中するあまり、結果を「ラベル貼り」にしてしまう失敗もあります。強みは変化するものなので、一度決めつけて終わりにしないことが重要です。また、強みは他者と比較する対象ではなく「自分らしさの源泉」として捉える視点を持ちましょう。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
ビジネスにおける強み活用コーチング

ビジネスの現場で「強みを活かすコーチング」を導入する企業は増えています。人材の強みを発揮させることで、生産性や組織の活力が高まるからです。
企業での活用シーン
- 人材育成
社員一人ひとりの強みを把握し、配置や役割分担に活かす。 - チームビルディング
メンバーの強みを共有することで、相互理解と信頼関係を促進。 - リーダーシップ開発
管理職が部下の強みに基づいてマネジメントを行う。 - 採用・配置
面接やアセスメントで強みを見極め、適材適所を実現。
事例
あるIT企業では、社員全員にストレングスファインダーを実施。チームで強みを共有し、互いの役割を調整しました。その結果、会議での意見交換が活発化し、プロジェクト達成率が120%に向上。
強みを活かした組織とそうでない組織の比較
| 項目 | 強みを活かしていない組織 | 強みを活かす組織 |
|---|---|---|
| 社員のモチベーション | 指示待ち・停滞感 | 自発的・挑戦的 |
| チームワーク | 個人主義・摩擦多い | 補完関係・協力的 |
| 生産性 | 横ばい | 向上 |
| 離職率 | 高い | 低い |
企業での強み活用は「人材の最適配置」に直結します。社員が自分の強みを認識し、それを周囲に共有するだけでチームの連携は向上します。また、強みをベースにしたフィードバックは受け手に安心感を与え、主体的な行動を引き出す効果があります。
キャリア設計と強みコーチングの関係

キャリアを考えるとき、多くの人は「需要のあるスキル」や「給料の高さ」を基準に選びがちです。しかし、それだけでは長期的に満足できない場合が多いのです。そこで重要なのが、自分の強みを軸にしたキャリア設計です。
強みを活かすキャリア設計のメリット
- 長期的にモチベーションを維持できる
- 転職やキャリアチェンジの際も方向性を見失わない
- 自然体で成果を出せるため、自己肯定感が高まる
事例
Hさん(20代・営業職)は「人前で話すことが苦手」と感じていました。しかし、コーチングを通じて「個別にじっくり相手の話を聞く力」が強みだと発見。営業スタイルを「大量アプローチ型」から「深掘りヒアリング型」に変えたところ、顧客満足度が高まり、契約件数も増加。キャリアの自信につながりました。
強みを軸にしたキャリア設計は「変化の多い時代」に適したアプローチです。スキルや知識は陳腐化しても、強みは本質的な資質として残ります。そのため、強みを中心にキャリアを描くことは、自分らしさを守りつつ柔軟に成長できる戦略となります。
強みを育てるセルフコーチングの方法
コーチと対話する以外にも、自分でできる「セルフコーチング」で強みを育てることが可能です。
ステップ
- 振り返りノートをつける
「今日できたこと」「楽しかったこと」「人から感謝されたこと」を記録。 - 強みリストをつくる
出てきたエピソードから強みを抽出してリスト化。 - 強みを小さく使う実験
例えば「共感力」が強みなら、1日1回だけ相手の感情を言葉にして返す。 - 成功体験を積み重ねる
小さな成功を記録していくことで、自信が育つ。
書き方例(ノート記入)
- 今日の行動で楽しかったこと:後輩に相談され、アドバイスできた
- 感謝されたこと:チームの会議資料をまとめた
- そこから見える強み:整理力、面倒見の良さ
- 次回に活かすアクション:来週の新人研修で進行役を担ってみる
注意点
- 書くことが「義務」になると続かないので、短文でもOK
- 強みは「毎日同じ」ではなく「状況によって変わる」ことを前提に
セルフコーチングで重要なのは「気づきを逃さない習慣」です。毎日の小さな振り返りが、強みを磨く材料となります。書き出すことで客観性が高まり、自分の行動に一貫性が生まれます。無理なく続ける工夫が成果を左右します。
まとめ|強みを軸に人生をデザインする

この記事では「強み」と「コーチング」の関係について解説してきました。
- 強みとは「自然体で繰り返し発揮される資質」である
- コーチングは質問と対話を通じて強みを引き出すプロセス
- 強みを知ることはキャリアや人生の満足度を高める
- ビジネスでも個人でも「強みを活かす組織・環境づくり」が鍵になる
- セルフコーチングでも強みを育てることができる
最も大切なのは「強みは固定されたものではなく、磨かれて育つ」という視点です。自分の強みを理解し、日々の行動に活かすことで、人生のあらゆる場面にポジティブな変化が生まれます。
あなたの中に眠る強みは、まだ見つかっていないだけかもしれません。コーチングを通じて、その可能性を解き放ち、自分らしい未来をデザインしていきましょう。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
透過②.png)







