「仕事に行きたくない時に読む処方箋|脳の仕組みから整える“やる気が出ない日”の対処法

朝、目覚ましの音が鳴っても体が動かない。「仕事に行きたくない」——そんな気持ちは誰にでも訪れます。
けれど、本当に大切なのは「無理して行く」ことではなく、「なぜ行けないのか」を理解すること。
この記事では、認知科学の視点から“脳の仕組み”を整え、やる気を自然に取り戻す方法を解説します。
仕事に行きたくないと感じるのは“甘え”ではない

「仕事に行きたくない」と感じる瞬間、多くの人が自分を責めてしまいます。
けれど、それは脳が発するSOSサインであり、甘えでも怠けでもありません。
まずは、脳の仕組みから「なぜ仕事がつらく感じるのか」を整理していきましょう。
仕事に行きたくない時、脳の中では何が起きている?
脳は常に「快」と「不快」を天秤にかけています。
仕事に対して“不快”が強くなると、脳はコンフォートゾーン(安心領域)に戻ろうとし、
結果として「行きたくない」という信号を出します。
例:「今日は上司に会いたくない」「ミスしたくない」など
→ 脳は“危険”と判断し、体を動かさないように命令している状態です。
これは自己防衛反応であり、悪いことではありません。
むしろ、心身を守るための自然な働きなのです。
「仕事のストレス」は“見えない敵”
脳は「目に見えないストレス」に特に弱い構造をしています。
たとえば「なんとなく不安」「この先どうしよう」など、明確な原因がないまま感じるストレス。
この状態が続くと、“本当の目的”や“自分のやりたい仕事”が見えなくなってしまいます。
【ポイント】
- 「仕事が嫌だ」という感情の裏には“何が嫌なのか”が隠れている
- それを可視化することで、脳の霧が晴れる
- 感情を責めるより「自分を観察」することが大切
仕事の“やる気”は「外」ではなく「内側」にある
多くの人は「上司の言葉」や「評価」など、外部要因でモチベーションを保とうとします。
しかし、認知科学的に見るとやる気は外から生まれるものではなく、内側から湧き上がるもの。
脳のRAS(網様体賦活系)は、
「自分が望むゴール」に意識が向いている時にのみ、エネルギーを生み出します。
つまり、“やらなきゃ”より“やりたい”が動力源です。
例:
・「上司に怒られたくないからやる」→ 一時的なやる気
・「自分の成長を実感したいからやる」→ 持続的なやる気
「仕事が嫌い」ではなく「自分が見えなくなっている」
本当は仕事そのものが嫌なのではなく、
“自分の価値観や目的が曖昧になっている”ことがつらさの正体です。
- 本当は「誰かに喜ばれる瞬間」が好きなのに、数字ばかり見て苦しくなる
- 本当は「チームで働くのが好き」なのに、孤独な環境で疲弊する
- 本当は「創造するのが好き」なのに、管理ばかり任される
脳は“自分の理想”と“現実”が離れるほど、ストレスを強く感じます。
このズレを埋めることが、「仕事に行きたくない」状態から抜け出す第一歩です。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事に行きたくないと感じる5つの原因|脳の状態から整理する

「仕事に行きたくない」という気持ちは、一言で言い表せるものではありません。
その背景には、脳が感じている5つの“疲れ”や“ズレ”が存在します。
ここでは、認知科学の視点からその原因を明確にし、今の自分に何が起きているのかを見つめ直していきましょう。
仕事に行きたくない原因①:脳が“過負荷モード”に入っている
脳は処理できる情報量に限界があります。
仕事で多くのタスク・人間関係・締め切りに囲まれていると、脳のワーキングメモリが飽和し、思考停止状態に。
この状態になると、RASが“停止信号”を出し、「もう行きたくない」という感情が強まります。
例:
- 朝から会議→報告書→クライアント対応が続く
- 「考えることが多すぎて何もしたくない」
- 「会社のドアを開けるだけで息苦しい」
過負荷モードでは、休むことより“考えを整理する”ことが回復の第一歩です。
脳のキャパシティを超えているときは、思考よりまず停止のサインを受け取る勇気を持ちましょう。
仕事に行きたくない原因②:目的と行動がズレている
脳が最もストレスを感じるのは、「やりたいこと」と「やっていること」が一致していない状態です。
これは、コンフォートゾーンのズレと呼ばれる現象。
例:
- 「人の役に立ちたい」→ でも、数字だけを追う仕事ばかり
- 「チームで動きたい」→ でも、孤立した業務が中心
このズレが続くと、脳はエネルギーを出さなくなります。
なぜなら、“目的の見えない行動”には報酬がないから。
つまり、モチベーションを取り戻すには目的を再設定することが鍵になります。
【ポイント】
- どんな瞬間に「自分らしい」と思えるかを思い出す
- 嫌な仕事より、“本当はやりたい仕事”に意識を向ける
仕事に行きたくない原因③:人間関係による認知ストレス
脳は人間関係の“曖昧さ”を最も苦手とします。
上司の表情や同僚の態度など、相手の反応を常に予測する状況では、脳は常時警戒モードになります。
例:
- 「また怒られるかも」
- 「嫌われてるかも」
- 「頑張っても認めてもらえない」
この状態では、脳のエネルギーが対人不安の処理に使われてしまい、
本来の“仕事思考”が機能しません。
結果として、仕事そのものが怖く感じるようになります。
→ 対処法は、「相手にどう思われているか」ではなく、
“自分がどう在りたいか”という主観に焦点を戻すことです。
仕事に行きたくない原因④:成果よりも“評価”が軸になっている
「上司の目が気になる」「周りと比べて落ち込む」——
このような思考が強いと、脳は常に他者基準のフィードバックループに閉じ込められます。
すると、行動の目的が「自分の意思」ではなく「評価回避」になり、やる気の源泉が枯れていきます。
【脳のメカニズム】
- 他者評価が軸 → “報酬系”が外部依存
- 自己基準が軸 → “報酬系”が内的活性化
つまり、評価を得るよりも“納得できる仕事”を選んだ方が、脳の報酬系が安定します。
「どう思われるか」ではなく「どう生きたいか」。
この視点が切り替わった瞬間から、仕事の捉え方は一変します。
仕事に行きたくない原因⑤:未来のゴールが見えていない
脳は「未来の映像」がないと、エネルギーを生み出せません。
ゴール(理想の状態)が曖昧なままでは、RASが“何を選べばいいか”を判断できず、思考が迷子になります。
例:
- 「何のために働いているかわからない」
- 「10年後の自分が想像できない」
この状態で努力しても、脳は報酬を感じません。
だからこそ必要なのは、“ゴールを描くこと”よりも、“自分がどうありたいか”を言語化すること。
そこから脳は自然に最適な行動を導き出します。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事に行きたくない朝にできる5つの対処法|心と体を同時に整える

「仕事に行きたくない」と感じたときに一番大切なのは、“無理に気持ちを変えようとしないこと”です。
私たちは「頑張らなきゃ」と思うほど脳が緊張し、余計に動けなくなってしまいます。
ここでは、気持ちを責めずに、自然と回復していくための5つの具体的ステップを紹介します。
仕事を“頑張る”より、まず休む勇気を持つ
体が動かないのは、怠けではなくエネルギー切れのサインです。
しっかり休むことで、脳の疲労が回復し、思考も前向きになります。
たとえば、1日休む、出社時間を少し遅らせる、午前休を取るなども立派な選択です。
例:
- 「今日一日だけでもいいから、心を休める時間をつくる」
- 「カフェで静かに過ごす」「通勤前に少し散歩する」
休むことは逃げではありません。
それは“次に動くための準備”です。
仕事のことを考えすぎる時間を減らす
「行きたくない」という気持ちは、頭の中で何度も考えるほど大きくなります。
いったん仕事から意識を切り離すことで、脳の負担を軽くできます。
スマホを見ない時間をつくる、音楽を聴く、外の空気を吸うなど、意図的に思考のスイッチを切ることがポイントです。
【コツ】
- 「考えない」よりも「別のことをする」
- 料理や読書、掃除など“没頭できること”を選ぶ
一時的に距離を置くことで、仕事に対して冷静な視点が戻ります。
仕事に行きたくない気持ちを言葉にする
気持ちを溜め込むと、心の中でどんどん膨らんでしまいます。
「行きたくない」「しんどい」「疲れた」など、率直に言葉にすることで、脳が状況を整理し始めます。
ノートに書き出したり、信頼できる人に話したりするだけでも効果的です。
【ポイント】
- “何がつらいのか”を文章にする
- 言葉にすることで、自分を客観的に見られるようになる
「言葉にする」は“自分を守る行動”のひとつ。
頭の中で抱えず、外に出すだけで心は少し軽くなります。
仕事に行きたくない理由を一つずつ分けて考える
「全部嫌だ」と感じると、どこから手をつけていいかわからなくなります。
そこで効果的なのが、「何が嫌なのか」を分けてみること。
たとえば以下のように整理してみましょう。
| 嫌なこと | コントロールできる? | 対処の方向 |
|---|---|---|
| 朝起きるのがつらい | △ | 睡眠リズムを調整する |
| 上司と話すのが怖い | ○ | メモを使って会話を減らす |
| 仕事内容が合わない | × | 異動・転職の検討 |
| 将来が見えない | △ | 自分の価値観を整理する |
すべてを解決する必要はありません。
「少し変えられる部分」から見つけることが、前進へのきっかけになります。
仕事に行きたくない時は“小さな行動”を一つだけ
気持ちが重い朝は、行動を細かく分けることが効果的です。
「起きる」「顔を洗う」「服を着る」「玄関まで行く」など、
一つずつの行動に集中すると、“できた”という小さな達成感が積み重なります。
例:
- 「とりあえず会社の前まで行ってみる」
- 「メール1通だけ返信してみる」
動けない時は、完璧を目指さず、“1つできた”を大切に。
それだけで、脳が「動けた」と認識し、次の一歩を出しやすくなります。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事を辞めたい・続けたいで迷う時の整理法|焦らず決めるための視点
-1024x685.jpg)
「もう限界かもしれない」「辞めたいけど不安」——
そんな風に仕事のことで頭がいっぱいになるとき、私たちは“白黒思考”に陥りがちです。
でも大切なのは、辞める or 続けるの二択で考えないこと。
一度、心の中を整理してみましょう。
仕事を辞めたい気持ちが強い時にやるべきこと
まずは、「辞めたい」と思う理由を明確にすることです。
感情だけで動くと後悔しやすくなりますが、理由を整理すると冷静になれます。
例:
- 上司との関係が限界
- 自分の成長を感じられない
- 仕事の内容が合わない
- 心身の不調がある
これらはすべて「自分の心が出しているサイン」。
焦らず、「今の自分にとって何がつらいのか」を書き出してみてください。
【ポイント】
- 「辞めたい」=逃げではなく“変化の兆し”
- 感情の整理ができると、冷静な判断ができるようになる
仕事を続けるべきか迷う時のチェックポイント
辞める決断をする前に、「今の職場に残る可能性」も一度見てみましょう。
環境を変えるだけで解決できるケースも多くあります。
【チェックリスト】
- 仕事内容は好きだけど、人間関係がつらい
- 上司が変わればやりやすくなる
- 部署異動や働き方の変更で改善できる
- 生活リズムを整えたら気持ちが変わる
すぐ辞めるのではなく、「残るための改善策」があるかどうかを確認する。
これだけでも、決断の精度が上がります。
仕事を辞めてもいいサインを見極める
一方で、無理をして続ける必要がない状況もあります。
下記のような状態が続いているなら、転職や休職を前向きに検討しても構いません。
【辞めてもいいサイン】
- 朝起きるのがつらく、体調が悪化している
- 職場を考えるだけで涙が出る
- 睡眠や食欲に影響が出ている
- 誰にも相談できず、孤立している
- 「このままでは自分が壊れそう」と感じている
ここまできたら、あなたの心と体が「限界です」と教えてくれている証拠です。
自分を守るための選択は、逃げではなく勇気のある決断です。
仕事を辞める前に整理しておきたい3つのこと
感情的にならず行動するためには、次の3点を整理しておくと安心です。
| 整理項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 生活面 | 貯金・支出・退職後の生活を試算しておく |
| ② 人間関係 | 相談できる人・支えてくれる人を明確にする |
| ③ 心の整理 | 何から離れたいのか/何を得たいのかを言語化する |
この準備があるだけで、次の一歩が「逃げ」ではなく「選択」になります。
仕事の決断をするときの合言葉
決断の場面で迷ったら、こう問いかけてみてください。
「この選択は、怖さからか、希望からか?」
怖さからの決断は後悔につながりやすく、
希望からの決断は、結果がどうであれ納得できます。
未来の自分が「よくやった」と言えるかどうか——そこに答えがあります。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事を続けると決めたら|気持ちを立て直すための5つのリセット習慣
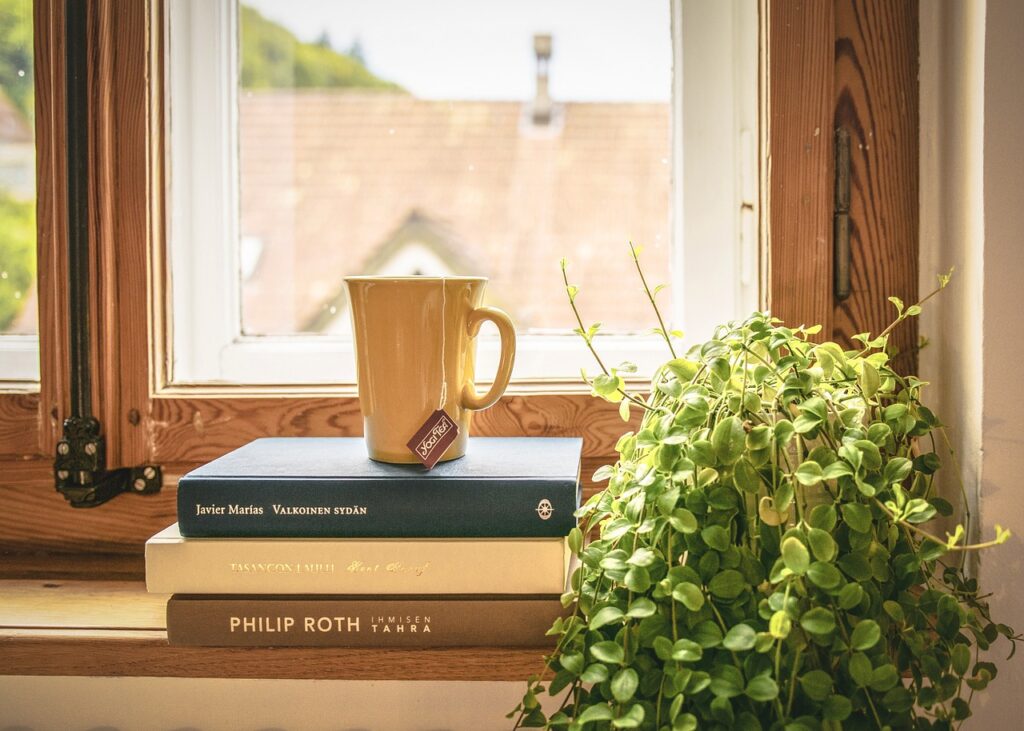
「辞める」ではなく「もう少し続けてみよう」と決めたあとも、すぐに気持ちが切り替わるわけではありません。
大切なのは、これまでと同じ働き方を続けないこと。
無理を積み重ねたままでは、また同じ壁にぶつかってしまいます。
ここでは、心をすり減らさずに仕事を続けていくためのリセット習慣を紹介します。
朝のルーティンを変えて“仕事スイッチ”をゆるめに入れる
朝の準備時間を少し工夫するだけで、気持ちの切り替えがスムーズになります。
たとえば、10分だけ早く起きて好きな音楽を聴く、温かい飲み物をゆっくり飲むなど、
“気持ちが整う時間”を作ることがポイントです。
例:
- 朝に「やる気を出す」より「心を落ち着ける」習慣をつくる
- 通勤中に仕事のことを考えず、好きな香りや音を感じる
“始まり方”が変わるだけで、その日の仕事の感じ方も変わります。
自分のペースで働くことを意識する
すべての人に合わせようとすると、必ず疲れます。
仕事を続けるためには、「自分のリズム」を守ることが大切です。
周囲が早くても、自分が丁寧にやる方が落ち着くなら、それを選んでいい。
【ポイント】
- 無理にスピードを合わせない
- 「自分はこれで大丈夫」と思えるペースを見つける
他人のリズムではなく、自分の呼吸で働くことが、継続の鍵です。
仕事の中に“小さな喜び”を見つける
やりがいを感じる瞬間は、意外と小さなところにあります。
「同僚にありがとうと言われた」「今日の資料が分かりやすくできた」
——そんな些細な出来事に意識を向けてみましょう。
例:
- “よかったことメモ”を毎日1つ書く
- 一日の終わりに「今日できたこと」を3つ思い出す
小さな喜びに気づける人ほど、仕事への安心感が高まります。
仕事で完璧を目指さない
「ミスしないように」「もっと頑張らなきゃ」と思うほど、脳は緊張し続けます。
完璧よりも“できた範囲を認める”姿勢を持つことで、心の余裕が生まれます。
【意識の切り替え】
- ×「全部できなかった」
- ○「ここまではできた」
“できた”を積み重ねることが、自信を取り戻すいちばん確実な方法です。
仕事を通じて「自分がどう成長しているか」を見つめる
忙しい日々の中で、自分の変化に気づくことは少ないものです。
でも、少し立ち止まって振り返ると、意外とたくさんの成長があります。
例:
- 昔より冷静に話せるようになった
- 苦手だった仕事を一人でこなせるようになった
結果だけではなく、“過程”の中にある変化を見つけていく。
それが、次の自信とエネルギーにつながります。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事のやる気が出ない日が続くときに試したい思考の整理法

誰にでも「今日はどうしてもやる気が出ない」という日があります。
でもそれが何日も続くと、「このままでいいのかな」「自分はダメなんじゃないか」と不安になりますよね。
やる気が出ないときに大切なのは、“動かそうとする”のではなく、“整える”こと。
ここでは、心を落ち着かせて前向きな思考を取り戻すための整理法を紹介します。
「やる気が出ない自分」を責めない
やる気が出ない日ほど、自分を責めてしまうものです。
でも、脳のエネルギーは常に一定ではありません。
考えすぎた次の日、ストレスが続いた週、睡眠不足の朝——。
それだけで脳の集中力や意欲は一時的に下がります。
例:
- 昨日うまくいかなかったから今日は怖い
- 忙しすぎて頭が休めていない
そんな時に必要なのは「やる気を出す」よりも「今は回復期なんだ」と認識すること。
回復期を責めないことで、自然とエネルギーは戻ります。
「何ができていないか」ではなく「何ができているか」に注目する
やる気が出ないとき、人は“できなかったこと”ばかり見てしまいます。
けれど、それでは脳が「自分はダメだ」と認識してしまい、さらに動けなくなります。
逆に“できていること”に目を向けると、脳は小さな達成感を感じ、再び動き始めます。
【例】
- 朝起きて出社できた
- メール1通返信した
- 同僚と笑顔で話せた
小さな成功を意識するだけで、脳が「もう一歩やってみよう」と指令を出しやすくなります。
仕事の目的を「やる理由」から「望む未来」に変える
「やらなきゃいけない」ばかり考えると、義務感で脳が疲れてしまいます。
そんな時は、「これをやった先に、どんな未来が待っているか?」に意識を向けてみてください。
例:
- 「報告書を早く提出しなきゃ」 → 「早めに終わらせて今日はゆっくりしたい」
- 「資料作らなきゃ」 → 「見やすい資料を作って褒められたら嬉しい」
人は“目的”よりも“感情”で動きます。
未来に少しでも「いい気分」があると、脳は自然とエネルギーを生み出します。
自分の思考を紙に書き出して“見える化”する
考えが頭の中をぐるぐる回っている時は、紙に書くのが一番効果的です。
不安や迷いを文字にすると、脳が「もう覚えなくていい」と判断し、余裕が生まれます。
【やり方】
- 今の気持ちを思いつくままに書く
- それを「変えられること」と「変えられないこと」に分ける
- 変えられる方から小さく動く
この“書く整理”は、仕事の悩みを客観的に見るのにとても有効です。
感情が整うと、行動の優先順位も自然と見えてきます。
「何もしない時間」を意識して作る
やる気が出ないときこそ、“何もしない時間”を持つことが大事です。
SNSも見ず、音も立てず、ただぼーっとする。
それだけで、脳の疲労は驚くほどリセットされます。
【コツ】
- 昼休みに5分だけ目を閉じる
- 仕事終わりに散歩して頭を空っぽにする
休むことに罪悪感を持たない。
それが、長く働き続けるための本当の「努力」です。
自分らしく仕事を続けるために大切な3つの視点

「仕事に行きたくない」という感情の奥には、
“自分らしさを見失っている”というサインが隠れています。
職場の環境や人間関係を変えることも大切ですが、
本当の意味で楽になるには、自分の中の軸を見直すことが欠かせません。
ここでは、今の仕事をどう捉え直すかを整理する3つの視点を紹介します。
「できる仕事」より「心が動く仕事」を意識する
私たちは、得意なこと=やるべきこと、と思いがちです。
けれど、本当に続けていける仕事は、“得意”より“好き”の方にあります。
うまくできるけど気持ちが乗らない仕事は、心をすり減らしやすい。
例:
- 事務処理は得意だけど、人と話す仕事の方が楽しい
- 数字は苦手だけど、企画を考える方がワクワクする
「できる仕事」と「心が動く仕事」が重なっている部分を探すこと。
それが、自分らしく働くための第一歩です。
「正解の働き方」を探さない
SNSや周囲の人と比べると、「自分は遅れているのでは」と感じることがあります。
でも、働き方に正解はありません。
フルタイムで働くのも、時短勤務にするのも、転職するのも、どれも選択のひとつです。
【ポイント】
- 周りに合わせるより、自分の心が落ち着く選択をする
- 「こうあるべき」ではなく「自分がどうありたいか」で決める
他人と比べる軸を手放すと、心がスッと軽くなります。
“自分のペースで働く”ことが、結果的に一番の成長につながります。
「仕事」だけで自分を測らない
人はつい、仕事での成果や役割で自分の価値を判断してしまいます。
でも、あなたの価値は職場の評価だけで決まるものではありません。
例:
- 家族や友人を大切にしている
- 趣味を通じて人を笑顔にしている
- 誰かを励ました経験がある
そうした“仕事以外の自分”も、あなたという人の大切な一部です。
働き方を整えるとは、生き方を整えることでもあります。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテの体験コーチングはこちらから!/
仕事でつらい時に支えになる人との関わり方

「仕事に行きたくない」と感じる時、多くの人が“誰にも話せない”状態になっています。
「弱音を吐いたら迷惑をかけるかも」「どうせ理解されない」と思ってしまう。
けれど、孤立したままでは脳も心も回復しづらく、気持ちがどんどん重くなっていきます。
ここでは、つらい時にこそ思い出してほしい“人との関わり方”を紹介します。
一人で抱え込まないことが、立ち直りの第一歩
人は、誰かに気持ちを話すだけでもストレスホルモン(コルチゾール)が下がると言われています。
つまり、「話す」という行為そのものが回復行動です。
相手に解決してもらう必要はなく、ただ話すだけでいい。
例:
- 「最近、ちょっとしんどくてね」と一言でも伝える
- メッセージで「聞いてほしい」と送る
それだけで、脳は「自分は一人じゃない」と感じて落ち着きを取り戻します。
人に頼ることは弱さではなく、生きる力を取り戻す行動です。
“分かってくれる人”を一人だけ持つ
誰にでも話せるわけではありません。
だからこそ、「分かってくれる人を一人持つ」ことが大切です。
それは家族でも、友達でも、職場の同僚でもいいし、
時にはカウンセラーやコーチのような専門家でも構いません。
【ポイント】
- 評価せずに聞いてくれる人
- アドバイスより共感してくれる人
- 「あなたのままでいい」と言ってくれる人
誰かに安心して話せる場があるだけで、「仕事に行きたくない」という気持ちは少しずつ薄れていきます。
“頼る”ことと“甘える”ことを分けて考える
多くの人が、人に頼ることを「甘え」と感じてしまいます。
でも、頼るとは“自分を助けてもらう仕組みをつくること”。
それは弱さではなく、自分を守る賢さです。
例:
- 仕事の優先順位を相談する
- 「今日は少し手伝ってもらえる?」と声をかける
- 家族に「今週は早く帰るね」と伝える
一人で背負いすぎず、少し周囲に委ねることで、エネルギーは確実に戻ってきます。
“話せる関係”を普段からつくっておく
いざという時に話せる人がいないと感じる人も多いでしょう。
その場合は、「日常の小さな会話」を増やすところから始めてみてください。
例:
- 同僚と「お疲れさま」と声をかけ合う
- カフェの店員さんに「ありがとう」と言う
- 家族に「今日こんなことがあった」と話す
人とのつながりは、急にできるものではありません。
だからこそ、日々の“ささやかな会話”が、いざという時の支えになります。
仕事を辞めたあとに後悔しないために|心の準備と整理のコツ

「もう限界かもしれない」「辞めるしかないかも」——そう感じて退職を決めた時、
少しホッとする反面、「本当にこれで良かったのかな」と不安になる人も多いでしょう。
けれど、辞めることは失敗でも逃げでもありません。
むしろ、自分を守るための新しいスタートです。
ここでは、辞めたあとに後悔しないための心の整え方を紹介します。
辞めることを“終わり”ではなく“始まり”と捉える
仕事を辞める時、多くの人は「これで終わりだ」と感じがちです。
でも実際は、“新しい自分を作る準備期間”が始まっただけ。
一度立ち止まるからこそ、次の方向が見えてきます。
例:
- これまでの働き方を見直す時間にする
- 新しい興味やスキルを探す時間にする
辞めることで空いた“余白”は、次の可能性を広げるスペースになります。
辞めたあとにやってはいけない3つのこと
退職後に多くの人が陥るのは、次のような行動です。
| やってはいけないこと | 理由 |
|---|---|
| ① 自分を責める | 「続けられなかった」と過去に意識が向く |
| ② 無理に次を決める | 焦りで選ぶと、同じ悩みを繰り返す |
| ③ SNSで他人と比べる | 他人のペースに飲み込まれ、自己肯定感が下がる |
退職後は“空白の時間”を怖がらず、心を回復させる時間として過ごすことが大切です。
焦りを手放すと、自然と次のチャンスが見えてきます。
「何を辞めたのか」を言葉にして整理する
辞めたあとに後悔が残るのは、「なぜ辞めたか」が曖昧なままだからです。
自分の中で、“どんなことから離れたかったのか”を明確にしておくと、次の選択に迷いません。
【書き出しの例】
- 「人間関係のストレスから離れたかった」
- 「自分の時間を取り戻したかった」
- 「安心して話せる環境がほしかった」
理由を整理しておくと、「あの時の決断は間違っていなかった」と思えるようになります。
仕事を辞めたあとにやるべき3つの行動
退職後の時間を有意義にするためには、心と体を整える3つの行動がおすすめです。
【ステップ】
- 睡眠と食事を整え、体を回復させる
- 散歩・旅行・趣味など、“自分の感覚”を取り戻す時間を作る
- 気持ちが落ち着いてきたら、“これからどう生きたいか”をゆっくり考える
「何をしたいか」がまだ見つからなくても大丈夫。
まずは、“今の自分を整える”ことが最優先です。
辞めたあなたに伝えたいこと
辞めたことで自信を失ったり、「続けられなかった自分」を責めてしまう人もいるでしょう。
でも、本当に強い人は“立ち止まる勇気”を持てる人です。
動き続けるだけが前進ではありません。
心を守る選択ができたこと、それ自体が大きな一歩です。
これからは、誰かの期待ではなく、自分のペースと感情を大切にできる働き方を探していきましょう。
そこから本当の意味で「仕事を楽しめる自分」が育っていきます。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事の悩みは「生き方のサイン」|人生全体を見直すタイミング

「仕事に行きたくない」と感じたとき、
それは単に仕事の問題ではなく、生き方を見直すタイミングでもあります。
働く時間は、人生の中で大きな割合を占めるもの。
だからこそ、仕事に違和感を覚えるのは「自分の生き方が少しずれているよ」という心の合図です。
ここでは、仕事をきっかけに“人生全体”を整える考え方を見ていきましょう。
「仕事」と「人生」を切り離さない
多くの人は、「仕事」と「プライベート」を分けて考えようとします。
けれど、実際には心も体も一つ。
職場でのストレスが家庭に影響したり、家庭の不安が仕事のやる気を下げたりします。
例:
- 仕事が忙しすぎて人間関係が疎遠になった
- 家族の悩みが気になって仕事に集中できない
この2つを切り離すのではなく、両方をどうバランスさせるかを考えることが大切です。
「仕事も人生の一部」と捉えることで、働き方がもっと自分らしいものに変わります。
仕事に感じる“モヤモヤ”の正体を見つける
仕事がつらい時ほど、「何が嫌なのか」がぼんやりしてしまいます。
でも、モヤモヤの正体を言葉にできると、一気に気持ちが整理されます。
【書き出しの質問例】
- どんな時に一番疲れる?
- どんな仕事なら時間を忘れられる?
- 今、我慢していることは?
自分の中の小さな違和感を拾うことが、“生き方を整える最初の一歩”です。
“理想の人生”を具体的に描いてみる
「仕事をどうしたいか」を考えるより、
「どんな人生を送りたいか」を先に描く方が、選択がぶれにくくなります。
理想の一日をイメージしてみましょう。
例:
- 朝はゆっくりコーヒーを飲みたい
- 自分の好きな時間に働きたい
- 家族との時間を優先したい
その理想の中にある“働き方の条件”が、次に選ぶ仕事のヒントになります。
「誰のために働きたいか」を考える
人は、自分のためだけに働くよりも、誰かのために働く方が力を発揮できます。
やる気や充実感は、「誰の役に立ちたいか」が明確になると自然に生まれます。
【例】
- お客さんの「ありがとう」にやりがいを感じる
- 同僚のサポートをすると嬉しい
- 家族を安心させたい
“自分の仕事が誰かを喜ばせている”と感じた瞬間、働く意味は変わります。
“仕事を整える”=“生き方を整える”
仕事の悩みを通して、自分の価値観が見えてくる。
それは決して悪いことではなく、成長のサインです。
何かがうまくいかないときほど、自分が何を大事にしているかが明確になります。
仕事は、あなたの生き方を映し出す鏡。
悩むこと自体が、より良い人生に向かっている証拠です。
やりたい仕事がわからない時に考えるべきこと|自分を知る3つの視点

「何がしたいのかわからない」「このままでいいのか不安」——
そんな迷いを感じている人はとても多いです。
けれど、やりたいことは“ひらめき”ではなく、“理解の積み重ね”から生まれます。
ここでは、焦らず自分を知っていくための3つの視点を紹介します。
①「できること」ではなく「気になること」に注目する
多くの人が、「自分にできること」から考えてしまいます。
でもそれでは、選択肢が“過去の延長”になりやすい。
むしろ大切なのは、「最近なんとなく気になること」「心が動くテーマ」に目を向けることです。
例:
- SNSでつい見てしまうジャンル
- 話していて時間を忘れる話題
- 疲れていてもやりたくなること
それが小さなヒントになります。
「やりたいこと」は“できる”の先ではなく、“気になる”の中に眠っています。
②「苦手なこと」の中にもヒントがある
避けてきたことや苦手に感じることの中にも、自分の本質が隠れています。
苦手なことは、実は「本気で向き合いたいけれど怖いこと」である場合が多い。
例:
- 人と話すのが苦手 → 実は人に興味がある
- 失敗が怖い → 本当は挑戦したい気持ちがある
苦手の中にある“本当の願い”を見つけると、自分の方向性がクリアになります。
避けてきたテーマほど、成長の鍵を握っていることが多いのです。
③「自分が大切にしたい価値観」を見つける
やりたいことを探すときに一番大切なのは、価値観の言語化です。
それは「何をしている時に自分らしいと感じるか」「どんな瞬間に幸せを感じるか」という問いの中にあります。
【質問例】
- どんな人を見て“素敵だな”と思う?
- どんな時に“これでいい”と心が落ち着く?
- 子どもの頃からずっと変わらないことは?
価値観が見えると、仕事選びも人間関係も自然に整っていきます。
“やりたいこと”よりも“どうありたいか”を見つめることが、結果的に長く続く仕事につながるのです。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事に対して前向きに動けない時の乗り越え方|行動を“努力”にしない方法
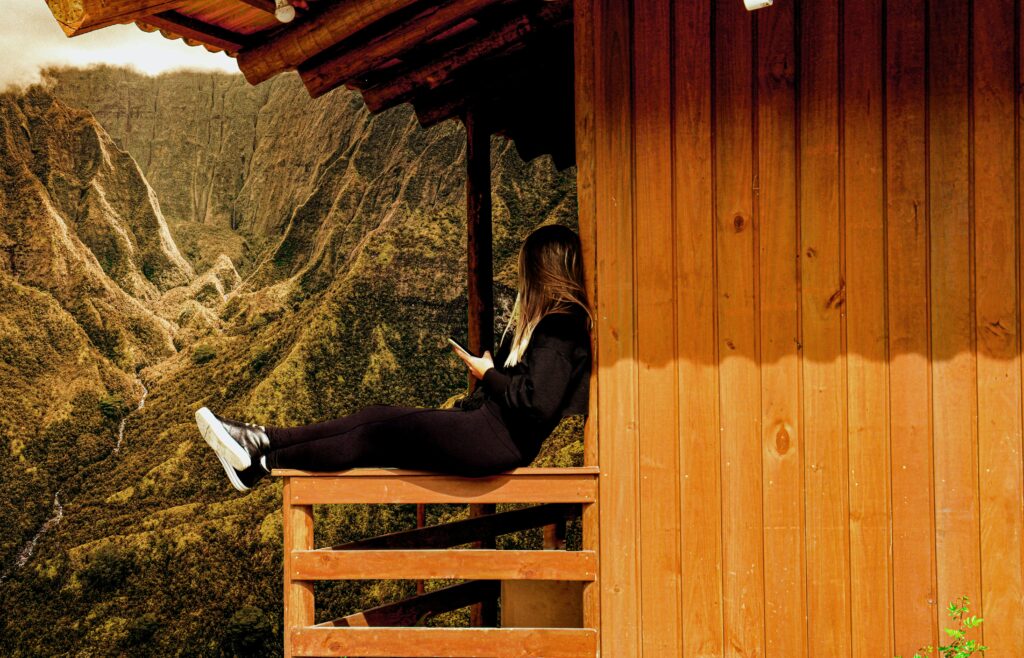
「動かなきゃいけないのは分かってるけど、体が動かない」
そんな時、私たちは“やる気がない”と思いがちですが、実際は違います。
脳は“安心できない状態”では、行動を止めようとするのです。
だからこそ、必要なのは“頑張る”ではなく、“整える”。
ここでは、自然に前に進めるための考え方を紹介します。
小さな行動を“成功体験”として扱う
行動のハードルを下げると、脳は「できた」と感じやすくなります。
たとえば、「転職活動をする」ではなく、「求人サイトを開くだけ」「履歴書の見出しを書く」でも十分です。
例:
- 「会社のホームページを見る」だけでもOK
- 「今日1件だけ連絡してみる」でもOK
小さな行動でも、“やれた”という体験が積み重なると、脳が安心して次の一歩を出せるようになります。
行動とは意志ではなく、安心の積み重ねなのです。
「完璧にやらなきゃ」をやめる
行動できない人の多くが、「どうせやるなら完璧にしたい」と思っています。
けれど、完璧を目指すほど脳の負担が増え、結果的に動けなくなります。
むしろ、「途中でやめてもいい」「ちょっとやってみよう」くらいの気持ちで大丈夫。
【ポイント】
- 完璧よりも“始めること”を優先する
- 完成よりも“動き出すこと”を目的にする
“完璧”を目指す努力ではなく、“少しずつ整える行動”に変えていく。
それが、長く続く力に変わります。
「自分を励ます言葉」を持っておく
行動の原動力になるのは、他人の言葉ではなく、自分自身の言葉です。
たとえば、「今日はここまでできたからOK」「焦らなくていい」など、
自分を安心させる言葉を持っておくと、行動が怖くなくなります。
例:
- 「できるところからでいい」
- 「昨日より一歩でも前に出たら十分」
- 「大丈夫、ちゃんと進んでる」
人は、自分の言葉でしか本当には動けません。
自分を責めるより、信じる言葉を習慣にすることが、前進のエネルギーになります。
「結果を急がない」意識を持つ
行動してもすぐに結果が出ないと、「意味がない」と感じてしまいます。
けれど、どんな変化にも“タイムラグ”があります。
行動の効果は、1週間後や1か月後、時には半年後に現れることも。
焦らず“今できること”を続けることが、確実な変化を生みます。
【例】
- 新しい仕事を探しながら、心も整えていく
- 毎日の小さな行動を記録してみる
変化は“少しずつ”訪れます。
だからこそ、焦らないことがいちばんの近道です。
仕事の意味を見失った時に思い出してほしいこと|自分の存在意義を取り戻す

「なんのために働いているんだろう」「自分の仕事に意味を感じられない」
そう感じる瞬間は、誰にでもあります。
でも実は、それは“終わり”ではなく、“深く生きようとしている証拠”です。
ここでは、仕事の意味を取り戻すための3つの視点を紹介します。
「誰のために働いているか」を見つめ直す
やりがいや目的を見失った時は、“誰のために働いているか”を考えてみましょう。
仕事は、誰かの生活や時間を支える行為です。
自分の手で、誰かが少しでも楽になったり、喜んでくれたりしているなら、
それはすでに“意味のある仕事”です。
例:
- コンビニで笑顔を向けるだけでも、誰かの気分を軽くしている
- 書類を整えることが、チームを助けている
- メール1通で、相手が安心できる
“誰かの役に立っている”という実感が、仕事の原点を取り戻してくれます。
「完璧な貢献」より「小さな誠実さ」
「もっと役に立ちたい」と思うほど、理想が高くなりすぎて苦しくなることがあります。
でも、社会を支えているのは“特別な人”ではなく、“誠実な人”です。
完璧にできなくても、誠実に関わることで、信頼は積み重なります。
【ポイント】
- できる範囲で力を出す
- 一人の人に丁寧に向き合う
- 嘘をつかず、真っ直ぐ対応する
その一つひとつが、あなたの存在価値を静かに育てています。
「仕事を通じて自分がどう在りたいか」を考える
意味を感じられない時ほど、“在り方”を意識することが大切です。
どんな職種でも、「自分がどう在りたいか」は選べます。
例:
- 誰かの話を真剣に聞く人でありたい
- 丁寧に仕上げる人でありたい
- 周りが安心できる存在でありたい
仕事の内容よりも、自分の“姿勢”に意識を向けると、日常の小さな行動が光り始めます。
どんな仕事も、あなたの在り方次第で意味が変わります。
「自分の存在が誰かの安心になっている」と信じる
私たちは自分の影響を過小評価しがちです。
けれど、あなたがいることで救われている人は必ずいます。
励ます言葉、笑顔、誠実な対応。
それらは、見えないところで人の心に残っています。
仕事の意味を見失ったときほど、
「自分がいるだけで誰かが安心しているかもしれない」
——そう思い出してみてください。
その視点が、もう一度あなたを現実に立たせてくれます。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事に行きたくない日があっても大丈夫|自分を責めずに生きるという選択

誰にだって、仕事に行きたくない日があります。
昨日まで平気だったのに、急に心が重くなる。
理由もわからず涙が出る。
そんな日があるのは、あなたが“真面目に頑張ってきた証拠”です。
「行きたくない」と感じるのは、怠けではなく心の防衛反応。
頑張りすぎたあなたの体と心が、「少し休もう」と伝えてくれているのです。
自分を責めるより、受け入れる
「みんな頑張っているのに」「自分だけ弱い」と思う必要はありません。
あなたの感じているつらさは、あなたにしかわからないものです。
まずは、自分の心の声を否定せずに受け入れてあげてください。
【自分への言葉】
- 「よくここまで頑張ってきたね」
- 「今日は無理しなくていい」
- 「また少しずつで大丈夫」
この“自分をいたわる言葉”が、再び立ち上がる力になります。
明日を少し軽くするためにできること
気持ちが沈む日は、未来のことを考えると苦しくなります。
そんな時は、「明日を少しだけ楽にすること」だけを意識してみてください。
例:
- 帰り道に好きな飲み物を買う
- 寝る前に好きな音楽を聴く
- 明日の服をお気に入りにする
小さな“楽しみ”を自分にプレゼントしてあげる。
それだけで、脳は「明日も悪くないかも」と感じてくれます。
人と比べない、自分のペースで生きる
誰かと同じスピードで進む必要はありません。
速く走る日があってもいいし、立ち止まる日があってもいい。
人生は競争ではなく、自分のペースで整えていく旅です。
周りに合わせて無理に頑張るよりも、
“自分の呼吸”で生きる方が、長く幸せが続きます。
「仕事に行きたくない日」が教えてくれること
この感情は、あなたが“自分を大切にしたい”という想いを持っている証拠です。
今まで気づけなかった本音や、心の疲れを知るきっかけになります。
そのサインに気づいた今こそ、少しずつ“自分の軸”を取り戻すチャンスです。
「仕事に行きたくない」と感じる日も、あなたの人生の一部。
その時間を丁寧に過ごすことで、次のステージがきっと見えてきます。
まとめ:仕事に行きたくない気持ちは“生きる力”の裏返し

ここまで読んでくれたあなたへ。
仕事に行きたくない気持ちは、決して弱さではありません。
それは、あなたが“本当の幸せ”を求めている証拠です。
焦らず、自分を責めず、少しずつ整えていきましょう。
そしてもし、自分の気持ちをもっと深く整理したくなったら——
「なないろ・コーチング」で、一緒に心を整える時間を持ってみてください。
あなたの中にある“本当の答え”を見つけるお手伝いができるはずです。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/

透過②.png)









