「仕事辞めたい」気持ちを整理する方法|逃げじゃなく“本音”からキャリアを考える
-scaled.jpg)
「仕事辞めたい」と感じる瞬間は、誰にでもあります。
でも、その気持ちをただ我慢したり、勢いで決断してしまうと、後悔につながることも少なくありません。
本記事では、認知科学の視点から「辞めたい」という心のサインを整理し、“逃げ”ではなく“本音”からキャリアを見つめ直す方法を解説します。
今の自分を理解する第一歩として、ぜひゆっくり読んでみてください。
「仕事辞めたい」と思うのは甘えではない|脳の防衛反応を理解する

「仕事辞めたい」という感情は、怠けや逃げではなく、脳が限界を知らせる自然なサインです。
多くの人は、「自分が弱いから」「我慢が足りないから」と思い込みますが、実はその感情の裏側には、脳の防衛本能が働いています。
この章では、「仕事辞めたい」と感じる心理の正体を、認知科学の視点でひも解いていきましょう。
「仕事辞めたい」と感じる瞬間に起きていること
人はストレスを感じると、脳の中で“防衛スイッチ”が入ります。
この状態では、集中力や判断力が落ち、物事をネガティブに捉えやすくなります。
つまり、「もうこの仕事無理かも」という思考は、あなたの意志ではなく脳の構造上の反応でもあるのです。
例:「朝、会社に行く準備をしているだけで動悸がする」「職場の人と話すのが怖い」
これは怠けではなく、脳が“これ以上危険だ”と感じている証拠です。
「頑張りすぎる人」ほど仕事がつらくなる理由
真面目で責任感が強い人ほど、自分の限界を超えても仕事を続けてしまう傾向があります。
認知科学的には、脳が「現状を維持したい」という“恒常性”を保とうとするため、ストレスを感じても“これまで通り頑張る”を選んでしまうのです。
頑張りすぎる人の特徴
- 仕事を休むことに罪悪感を感じる
- 仕事を任せるのが苦手
- 「自分だけ我慢すればいい」と思ってしまう
こうした思考パターンは、仕事中心の自己評価を強化してしまいます。
「仕事ができない=自分の価値がない」と錯覚してしまうのです。
「辞めたい」の奥にある“本音”とは
「仕事辞めたい」という言葉の裏には、本当はこうしたいという“もう一つの声”が隠れています。
それは「もっと自分らしく働きたい」「安心して挑戦できる環境で力を発揮したい」といったポジティブな欲求です。
例:「本当はやりがいのある仕事がしたい」「感謝される瞬間を感じたい」「人の役に立ちたい」
これらの感情は、辞めたい気持ちの“反対側”に存在しています。
認知科学では、人の行動を左右するのは**「何を避けたいか」ではなく「何を望んでいるか」です。
辞めたいという衝動を押さえ込むよりも、「自分は何を望んでいるのか」に焦点を当てることで、仕事に対する本音が見えてきます。
「仕事辞めたい」を整理する3つの問い
感情を整理する第一歩は、問いを変えることです。
脳は質問に対して答えを探す性質を持っているため、適切な質問を投げかけることで、思考の焦点が変わります。
自分に問いかけてみよう
- 今の仕事で「つらい」と感じる瞬間はどんなとき?
- 本当はどんな仕事をしているときに安心や充実を感じる?
- どんな働き方をしているとき、自分らしさを感じられる?
この3つの質問を通じて、「辞めたい理由」ではなく「自分が求めている働き方」が少しずつ見えてきます。
「仕事を辞めたい」は変化のサイン
実は、「仕事辞めたい」という感情は、脳が次のステージに進む準備をしているサインでもあります。
成長や変化を望むとき、脳は一度“違和感”や“葛藤”を感じます。
それがまさに、「今の仕事が合わない」「別の道を探したい」という気づきにつながるのです。
例:「今の仕事を続けても成長が見えない」「このままの人生でいいのか不安」
これらの悩みは、変化へのスタート地点に立っている証拠です。
「辞めたい」という感情を否定せず、「自分がどう変わりたいのか」という視点を持つこと。
それこそが、後悔しない選択につながる第一歩です。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
なぜ「仕事辞めたい」気持ちが強くなるのか|環境・思考・感情の3要因

「仕事辞めたい」という感情が強くなるとき、多くの人は「上司が合わない」「給料が安い」「成長できない」といった外的要因に目を向けます。
しかし、実際には「環境」だけでなく、「思考のパターン」や「感情の扱い方」など、自分の内面との関係性も深く関わっています。
この章では、仕事を辞めたい気持ちが強くなる3つの主要因を整理していきます。
環境要因|“合わない職場”が脳を疲弊させる
職場環境が合わないと、脳は常にストレス状態にさらされます。
特に日本では、「人間関係」「上司との価値観のズレ」「過剰な責任感」などが、仕事辞めたい理由ランキングの上位を占めます。
これは単なる不満ではなく、安全欲求が脅かされている状態です。
例:「上司の顔色を伺うのが疲れる」「会議で意見を言えない」「感謝されることがない」
こうした状況では、脳が常に“防御モード”になり、やる気や集中力が下がります。
認知科学的には、脳は「危険」と感じる環境では成長よりも防衛を優先します。
つまり、あなたの“辞めたい”という気持ちは、実は脳が「これ以上ここにいると消耗する」と判断している合図なのです。
ポイント
- 合わない職場では、自己肯定感が下がりやすい
- 無意識に“自分が悪い”と責める傾向が強まる
- 仕事の本質より「人の目」が中心になり、疲弊が増す
仕事の疲れを「頑張りが足りない」と誤解せず、環境が合わない可能性も冷静に見直すことが大切です。
思考要因|「~すべき」が多いほど苦しくなる
「仕事辞めたい」と強く感じる人の多くは、思考の中に「〜すべき」「〜でなければならない」という義務的思考が根強くあります。
これは一見まじめで責任感のある考え方に見えますが、実は自分の自由を奪う思考のクセでもあります。
よくある“〜すべき”の例
- ミスをしてはいけない
- 周りに迷惑をかけてはいけない
- 仕事は我慢して続けるものだ
このような考え方を続けると、常に「正解探しのモード」で脳が働き、エネルギーを消耗します。
そして次第に「自分が何をしたいのか」がわからなくなり、“辞めたい”という感情でしか本音を表現できなくなるのです。
例:「本当は転職したいけど、親が反対しそう」「自分が抜けたら職場が困るから辞められない」
このような思考の根底には、“自分の幸せより他人の期待を優先してきた”構図があります。
認知科学の観点では、この状態を「外的基準モード」と呼びます。
常に“外”に意識を向けているため、自分のゴール(内的基準)を見失うのです。
つまり「辞めたい」と感じるのは、“自分の軸を取り戻したい”という心の声でもあります。
感情要因|抑えこんだ感情が爆発するとき
もう一つの大きな要因は、感情を押し殺して働き続けることです。
仕事をする中で、怒り・悲しみ・不安などを我慢し続けると、脳がそれを「危険」と認識し、限界サインとして“辞めたい”を引き起こします。
例:「上司に理不尽なことを言われても笑顔で返す」「本当は泣きたいのに我慢して働く」
こうした“感情の抑圧”は、心身のバランスを崩しやすくなります。
感情は悪者ではなく、“自分の状態を教えてくれるセンサー”です。
特に「怒り」は、本当は何を大切にしたいかを示すサインでもあります。
たとえば「こんな働き方は違う」と感じる怒りは、「もっと成長したい」「認められたい」という願いの裏返しなのです。
感情を整理する3ステップ
- 感じたことを否定せずに言語化する(例:「腹が立った」「悲しかった」)
- その感情の奥にある“本音”を探る(例:「認めてほしかった」「安心したかった」)
- その本音を叶えるためにできる行動を考える
このプロセスを繰り返すことで、感情の暴走が落ち着き、仕事に対する視点も変わっていきます。
「仕事辞めたい」と感じたときに大切なのは“原因を混同しない”こと
多くの人は、「仕事がつらい=今の会社が悪い」と思いがちです。
しかし実際は、環境・思考・感情のどれが主な要因なのかによって、取るべき行動はまったく異なります。
原因別のアプローチ
| 原因タイプ | 対応方法 |
|---|---|
| 環境が原因 | 人間関係・業務量を見直す/転職・部署異動も選択肢に |
| 思考が原因 | 自分の価値観・目的を明確にする/自己理解コーチング |
| 感情が原因 | 感情を安全に表現できる場を持つ/休養・相談 |
「辞めたい」と感じるのは、“逃げ”ではなく“整理が必要”というサイン。
大切なのは、感情を無理に抑え込まず、自分の思考と感情を分けて見つめ直すことです。
感情的に動く前に、「今の仕事の何が自分を苦しめているのか?」を明確にすること。
それが、後悔しないキャリア選択の第一歩になります。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事を辞めるべきか迷ったときの判断基準|感情と現実を分けて考える

「仕事辞めたいけど、辞めていいのかわからない」
多くの人が最も迷うのは、まさにこの段階です。
一時的な感情なのか、それとも本当に限界なのか。
感情の波に飲まれず冷静に判断するためには、「主観」と「客観」を分けて考える必要があります。
この章では、辞めるべきサインと、踏みとどまるべきサインを明確にしていきましょう。
感情のサイン|「限界の赤信号」が出ているとき
まず見逃してはいけないのは、体や心が限界を訴えているサインです。
「仕事のことを考えると眠れない」「朝から涙が出る」「通勤が怖い」といった症状がある場合、それはもう理性ではなく脳の防衛反応です。
例:「仕事中、突然息が苦しくなる」「週末も不安で休めない」
これは“甘え”ではなく、心身がSOSを出している証拠。
認知科学的には、ストレスが一定を超えると脳の前頭前野(思考・判断を司る領域)が働かなくなり、思考が極端化(白黒思考)することがわかっています。
「もう全部イヤだ」「辞めるしかない」という思考が続くときは、まず休息が最優先です。
チェックポイント
- 睡眠・食事・呼吸のリズムが崩れている
- 職場に行くと動悸や吐き気が出る
- 休日も仕事のことが頭から離れない
これらに当てはまる場合、判断を急がず一度休む・距離を取ることが大切です。
休むことは逃げではなく、「判断するための体力を取り戻す」行為です。
現実のサイン|努力しても状況が変わらないとき
次に見るべきは、現実的な改善可能性です。
努力しても職場環境や人間関係が変わらない場合、それはシステムとしての限界に達しているサインです。
例:「改善案を出しても上司に却下される」「人手不足がずっと続いている」「評価制度が形骸化している」
こうした職場では、個人の努力よりも“構造的問題”が原因になっていることが多い。
特に注意したいのは、「我慢すればなんとかなる」と考えること。
これは一見ポジティブですが、脳の“現状維持バイアス”が働いている状態です。
認知科学では、変化を恐れる脳の性質をコンフォートゾーンの固定化と呼びます。
ここに長くいると、新しい可能性を見つける思考力が低下してしまうのです。
行動の目安
- 6ヶ月以上、同じ問題に悩み続けている
- 周囲も同じ不満を口にしている
- 会社の価値観と自分の理想が明らかにズレている
この3つが重なっている場合は、環境を変える決断を検討してもいい段階です。
価値観のサイン|「何のために仕事をしているか」が見えないとき
「仕事辞めたい」という気持ちが強くなる背景には、自分の価値観とのズレが隠れていることが多いです。
人は、自分の大切にしたい価値観に沿って行動しているときに最もエネルギーが高まります。
逆に、「何のために働いているのかわからない」と感じると、脳は“意味喪失”状態になります。
例:「毎日同じことの繰り返し」「誰のための仕事なのか見えない」
これは、報酬や安定では満たせない“内的ゴール”が欠けている状態です。
価値観を再確認する3つの質問
- 仕事を通して何を成し遂げたい?
- どんなときに「やってよかった」と感じる?
- どんな人と働いているとエネルギーが上がる?
これらを紙に書き出すだけでも、自分が“辞めたい”のか“方向を変えたい”のかが整理されます。
「価値観がズレている」だけなら、転職や異動でも解決することが多いのです。
周囲のサイン|誰にも相談できなくなったとき
人は孤立すると、思考が閉じ、視野が狭くなります。
もし最近、職場や友人に仕事の話をできていないなら、それも危険なサイン。
感情を外に出せないと、脳内に“未処理情報”が溜まり、エネルギーを奪います。
例:「話しても理解されないと思って黙ってしまう」「家族にも本音を言えない」
そんなときこそ、信頼できる第三者に話すことで思考が整理されます。
認知科学的には、人に話す行為は“外在化”と呼ばれ、脳内の情報を可視化して整理する効果があります。
言葉にするだけで、自分の考えがまとまり、感情の混乱が静まるのです。
話す相手の選び方
- 評価せずに聞いてくれる人
- アドバイスよりも共感してくれる人
- あなたの「本音」を引き出してくれる人
これらを満たす関係性がない場合は、コーチングやカウンセリングなどの専門的対話も選択肢です。
感情を整理する場を持つことで、「辞める・辞めない」を越えた新しい視点が得られます。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事辞めたいと思ったときに最初にやるべき整理|感情を見える化する

「仕事辞めたい」と感じた瞬間、多くの人が“辞めるかどうか”という二択に急ぎます。
しかし実は、その前にやるべきことがあります。
それは、感情の整理と原因の見える化です。
焦って行動する前に、心の中で起きていることを言葉にする。
それが、後悔しない選択の第一歩です。
感情をそのまま書き出す
辞めたい気持ちを抱えたとき、まずやってほしいのは「感情の書き出し」です。
頭の中で考えるだけでは、思考がループしてしまいます。
紙に書くことで、脳のワーキングメモリが解放され、冷静に全体を見渡せるようになります。
例:「もう限界」「上司の言葉が頭から離れない」「頑張っても報われない」
こうして文字にすると、“自分が何に疲れているのか”が具体的に見えてきます。
書き出しのコツ
- 「〜すべき」は一旦忘れて、思ったまま書く
- 感情を評価せず、“そのまま”受け止める
- 10分間だけ集中して、書き切る
認知科学では、感情を言葉にする行為を「ラベリング」と呼びます。
これは脳の扁桃体(感情の中枢)を静める効果があり、混乱を鎮めて論理的思考を取り戻す手法としても有効です。
仕事辞めたい理由を分類してみる
感情を整理したあとは、「辞めたい理由」を3つの視点で分けてみましょう。
ただ“イヤ”と感じるだけでなく、「何が」「どの程度」「どんな影響を与えているか」を可視化します。
辞めたい理由の3分類
| 分類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 環境型 | 職場の構造・人間関係・待遇など | 「上司との関係が悪い」「給料が低い」 |
| 自己認識型 | 価値観・モチベーション・ゴールの不一致 | 「成長を感じられない」「やりたいことが見えない」 |
| 健康型 | 精神的・身体的な限界 | 「朝起きられない」「常に不安がある」 |
この分類を使うと、**「何が本質的な原因か」が整理できます。
特に自己認識型の悩みは、外的変化よりも内的対話(自己理解)**で解決できることが多いです。
問題と本音を切り分ける
「仕事辞めたい」という言葉の中には、本音と表層の問題が混ざっています。
本音を見誤ると、転職してもまた同じ壁にぶつかります。
例:「上司が嫌い」は表層の問題。
その下にある「自分を認めてほしい」「挑戦できる環境で働きたい」が本音。
切り分けのステップ
- 「この仕事で何が一番つらい?」と問いかける
- 「その状況で、何が満たされていない?」を探る
- 「満たされない状態を変えるために、何ができる?」を考える
このプロセスで、「辞めたい=逃げ」ではなく、「変わりたい=成長欲求」として再定義できます。
例:「仕事辞めたい」→「もっと自分の意見を言える環境で働きたい」
感情を“行動可能な言葉”に変えると、次の選択肢が見えてきます。
感情を整える3つのルール
感情が整理されていないまま行動すると、衝動的な選択になりがちです。
まずは**「自分の心を整えるルール」**を設定しましょう。
感情整理の3ルール
- 感情を否定しない(泣く・怒るを許可する)
- 感情を一人で抱え込まない(話すことで処理される)
- 感情の正体を言語化する(“モヤモヤ”を“言葉”に変える)
例:「疲れた」と思ったら、「何に疲れたのか?」まで言語化してみる。
すると“人間関係”や“自己評価”など、根本原因が見えてきます。
この過程を経ることで、仕事の何を変えるべきかが明確になります。
「辞めるべきか」「続けるべきか」は、感情を整えてから考えるのが鉄則です。
書き出したあとに見えてくる3つの気づき
実際に感情を書き出すと、多くの人が次の3つに気づきます。
1. 思っていたより“人間関係”の影響が大きい
仕事内容よりも、人間関係のストレスが大きいことに気づく人が多いです。
職場の信頼関係が崩れると、どんなに好きな仕事でも続けるのが難しくなります。
2. “やりたい仕事がない”のではなく、“やり方が合っていない”
自分の特性や思考パターンを理解できていないだけで、仕事そのものを嫌いになっているケースがあります。
3. “本音”はいつも静かな声で存在している
焦りや怒りの裏に、「本当はこう生きたい」という穏やかな願いがある。
それに気づけるかどうかが、人生の方向を左右します。
仕事を辞める前にできる選択肢を整理する|“白か黒か”の思考を手放す
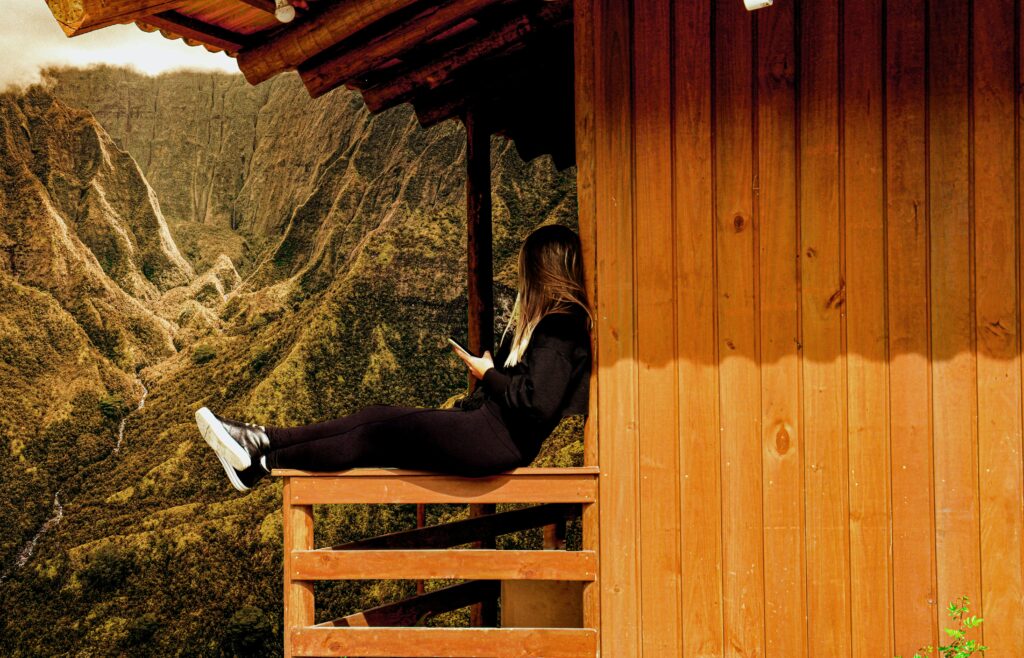
「仕事辞めたい」と感じると、多くの人は“辞めるか続けるか”の二択思考に陥ります。
しかし実際には、その間に無数のグラデーションがあります。
辞めるという決断をする前に、自分を守りながら現実を変える選択肢を一度整理してみましょう。
認知科学の視点でいえば、これは「焦点化」から「拡張」へのシフト。
見えていない選択肢に気づくことで、思考が柔軟になり、ストレスが軽減されます。
① 異動・部署変更を検討する
「仕事がつらい」と感じるとき、その原因は仕事内容そのものではなく、環境との相性であることが多いです。
同じ会社でも、上司・チーム・仕事内容が変わるだけで、脳の負荷は大きく減ります。
例:「営業がつらいと思っていたけど、企画部では楽しく働けた」
「職場の雰囲気が変わっただけで、仕事へのモチベーションが戻った」
ポイント
- 信頼できる上司・人事に正直に相談してみる
- 「辞めたい」ではなく「今の仕事の進め方を変えたい」と伝える
- 異動希望の理由は“前向きな言葉”で表現する(例:「自分の強みを活かせる部署で貢献したい」)
職場の中での移動は、リスクを最小限にしながら自分に合う仕事を再発見するチャンスです。
② 働き方を変えてみる
フルタイム・残業・出社といった“型”が合わないことで、仕事が苦しくなっているケースもあります。
一度、働き方の構造を見直すことで、心の余白が生まれます。
選択肢の例
- 時短勤務やリモートワークを相談する
- 業務の一部を外注化・分担化して負担を減らす
- キャリアチェンジに向けて副業や学びを始める
例:「週1リモートになってから、仕事を続ける余裕ができた」
「副業を通して、自分のやりたい方向が見えた」
認知科学的には、“選択肢を持つ”ことが自己効力感(エフィカシー)を高める要因になります。
「辞めるしかない」と思っていた状況でも、「変える手段がある」と認識するだけで、脳のストレス反応が下がります。
③ 休職・一時的な距離を取る
もし心身の限界を感じているなら、一時的に休むという選択も立派な方法です。
多くの人が「休職=終わり」と誤解していますが、実際には“リセットの時間”を取ることで回復し、再スタートできる人も多くいます。
休職が必要なサイン
- 朝、起きた瞬間に仕事の不安で動けない
- 出勤を考えただけで吐き気や動悸がする
- 休日も常に仕事のことを考えている
例:「2週間休んだだけで、頭がクリアになり、“自分は何に疲れていたのか”がわかった」
「距離を取ったことで、冷静に次の仕事を考えられるようになった」
休むことは“逃げ”ではなく、“再構築のための戦略”。
脳科学的にも、休息中に脳は情報を整理し、次の行動に向けた再学習を行います。
無理に動き続けるより、一度立ち止まる方が“結果的に早く前に進む”こともあるのです。
④ 「辞めたあとの生活」を仮設計してみる
もし辞める可能性が現実的に浮かんできたら、次に考えるべきは「辞めた後どうするか」。
これは“覚悟を固める”というより、“現実的な安心材料”を増やすための作業です。
整理すべき3ポイント
- 経済面:半年分の生活費・保険・失業給付などを確認
- 行動面:転職活動・資格・スキルアップの準備
- 精神面:支えてくれる人・相談できる場所の確保
例:「辞めたあとのお金の計算をしたら、思っていたより安心できた」
「転職活動を始めたことで、辞めるかどうかを冷静に判断できた」
ここで大切なのは、“辞める前提”で行動してもいいということ。
行動してみることで、「意外と今の仕事も悪くない」と気づくケースもあります。
動くことで見える選択肢は、机上の悩みよりもずっとリアルです。
⑤ 「仕事の辞め方」より「生き方の整え方」を考える
最終的に忘れてはいけないのは、辞めること自体が目的ではないということ。
仕事を辞めたい気持ちの奥には、たいてい「もっと自分らしく生きたい」という人生全体のテーマがあります。
例:「本当は人と関わる仕事がしたい」「家族との時間を大切にしたい」
「自分に正直に生きたい」
辞める・辞めないはあくまで手段であり、“自分の生き方”を整えるためのプロセスです。
認知科学コーチングでは、この「生き方の再設計」を“ゴール再定義”と呼びます。
今の環境をどう変えるかよりも、「自分が何を大切にしたいのか」に焦点を当てることで、本質的な選択ができるようになります。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事を辞めたいけど不安で動けないときの心理と対処法|「怖い」は悪者じゃない

「仕事辞めたい」と思っても、いざ行動しようとすると怖くて動けない。
そんな自分を責めていませんか?
実は、“不安”はあなたが怠けている証拠ではなく、脳が未知を警戒しているだけです。
この章では、その「怖さ」をどう扱えばいいのかを解説します。
不安の正体は「未来の自分を想像できないこと」
人が不安を感じるのは、未来が見えないときです。
仕事を辞める=未知の環境に飛び込むということ。
脳は“見えない未来”を「危険」とみなし、あなたを守ろうとします。
その結果、「このまま続けたほうが安全かも」という現状維持バイアスが働くのです。
例:「辞めた後どうなるかわからない」「次の仕事が見つからなかったらどうしよう」
これらは“現実的な問題”というより、“未来を想像できない恐怖”です。
認知科学的には、脳は「見える化」できたものしか信じられない構造を持っています。
だからこそ、まず必要なのは「不安を消すこと」ではなく、「未来を具体的に描くこと」なのです。
不安を整理する3ステップ
感情をコントロールする第一歩は、不安を“分解”して書き出すことです。
曖昧なまま抱えていると、脳が危険信号を出し続けます。
不安の整理ステップ
- 不安を書き出す(例:「お金がなくなる」「転職できない」)
- それぞれの不安に“現実度”を0〜100でつける
- 対策できるもの/できないものを分ける
例:「お金がなくなる→貯金3ヶ月分ある→現実度40%」
「転職できない→今まで2社経験ある→現実度30%」
こうして数字で可視化すると、思っていたより“根拠のない不安”が多いことに気づきます。
脳は「曖昧なもの」に過剰反応するため、見える形にするだけで安心感が生まれるのです。
行動の小さな一歩を決める
不安が大きいときほど、行動を小さく分解することが大切です。
「辞めるかどうか」ではなく、「今週できる1つの行動」を決めてみましょう。
行動の例
- 信頼できる同僚に気持ちを話してみる
- 転職サイトを1つだけ見てみる
- ノートに「理想の働き方」を3つ書く
例:「求人を眺めているうちに、“やってみたい仕事”が見えてきた」
小さな行動でも、“行動した実感”が脳に成功体験として刻まれます。
認知科学では、この“できた”感覚を「エフィカシー(自己効力感)」と呼びます。
エフィカシーが高まるほど、不安は自然に小さくなります。
つまり、不安を消すのではなく、成功体験で上書きするのがコツです。
不安を味方に変える思考法
不安は行動を止める敵ではなく、行動の方向を教えてくれるコンパスです。
「怖い」と感じる方向こそ、脳が“成長を察知している”証でもあります。
例:「転職が怖い」=新しい環境に挑戦したい
「人に話すのが怖い」=本当は分かってほしい
不安の裏側には、必ず「本当はこうなりたい」という願いが潜んでいます。
それを見逃さずに拾うことが、次の行動を決めるヒントになります。
不安を味方にする3つの質問
- この不安が教えてくれている“望み”は何?
- この不安を乗り越えたら、どんな自分になれる?
- 不安がある状態でも、今できる一歩は?
こう問いかけることで、不安は“立ち止まらせるブレーキ”から“方向を示すガイド”に変わります。
「仕事辞めたいけど怖い」その状態がチャンス
不安と向き合う時間は、実はチャンスです。
それは、あなたが「自分の人生を自分で選びたい」と感じ始めた証拠だから。
不安を完全になくすことはできませんが、不安を抱えたまま動くことは誰にでもできるのです。
例:「怖くても、自分で選びたい」
その一歩を踏み出せる人ほど、未来を自分で創る力を持っています。
「怖い」は悪者ではありません。
それはあなたの可能性が広がる前触れ。
不安を味方につけた瞬間、辞めるかどうかではなく、「どんな未来を生きたいか」が見えてきます。
仕事を辞めた後の自分をどう立て直すか|“空白期間”をチャンスに変える

「仕事辞めたい」という決断をしたあと、多くの人が直面するのが“空白の時間”です。
辞める前は「解放されたい」と思っていたのに、いざ自由になると、焦り・罪悪感・孤独感が押し寄せる。
これは自然な現象であり、脳の構造的反応でもあります。
この章では、仕事を辞めた後に訪れる“空白期間”を、再スタートのためのエネルギーに変える方法を紹介します。
「何もしていない自分」が怖くなる理由
辞めた直後に多くの人が感じるのが、「何もしていないことへの不安」。
これまで毎日“仕事”という予定で満たされていた時間が突然なくなると、脳が空白を危険とみなすのです。
このとき、焦って次の仕事を探そうとする人も多いですが、まずは何もしない時間を許すことが重要です。
例:「1週間休んだだけで罪悪感を感じる」「朝起きても“やることがない”と不安になる」
これらは怠けではなく、脳が“新しいリズム”に慣れていないだけです。
認知科学的には、人の脳は「安定したパターン」を維持したがる傾向があります。
仕事を辞めることでそのパターンが崩れるため、一時的に“不安定さ”が増すのは正常なプロセス。
この時期に必要なのは、「焦って動く」よりも「自分を観察する」姿勢です。
“空白期間”を自己理解の時間に変える
辞めた後こそ、自分を深く理解するチャンスです。
日々の仕事に追われていたときには気づけなかった、自分の思考・感情・価値観に向き合う時間が生まれます。
自己理解の3ステップ
- 「今の気分」「頭に浮かぶ言葉」「印象に残っている出来事」をノートに書く
- その中で「心が動いた瞬間」に印をつける
- なぜ心が動いたのかを掘り下げる
例:「上司に感謝されたとき嬉しかった」→「人に必要とされたい」
「一人で作業していると安心した」→「静かな環境を好む」
こうした“内的データ”を集めることで、次に選ぶ仕事が「何となく」ではなく、「根拠ある選択」になります。
自己理解とは、外の世界ではなく自分の中の羅針盤を見つける作業です。
「次の仕事を探す前に」整理しておきたい3つの軸
焦って転職サイトを見る前に、自分の中の3つの軸を明確にしましょう。
これを定めてから動くと、次の職場選びで迷わなくなります。
| 軸 | 意味 | 具体例 |
|---|---|---|
| 成長軸 | どんなスキル・経験を伸ばしたいか | 人との信頼関係/企画力/発信力 |
| 貢献軸 | 誰に、どんな価値を届けたいか | 若者/高齢者/地域社会/企業 |
| 生活軸 | どんな働き方をしたいか | 時間・場所・収入・人間関係 |
例:「地方に住みながらリモートで人の相談に乗れる仕事をしたい」
「自分の発信で誰かを励ませる働き方がしたい」
この3軸を持つことで、「辞めた後どうすればいいかわからない」が「こうしていきたい」に変わります。
“何もしない時間”の中で脳は整っている
何もしていない時間も、実は脳の中では情報の整理と再構築が行われています。
これを「デフォルトモード・ネットワーク」と呼び、創造性や自己洞察に関係する重要な機能です。
つまり、ぼーっとする時間や散歩の時間も、次の一歩に必要な準備期間なのです。
例:「何もしていない時間に、ふと“自分の好きなこと”を思い出した」
「休んでいる間に“また誰かの役に立ちたい”と思えるようになった」
仕事を辞めた直後は、“動くこと”よりも“整えること”を意識してください。
焦らずに心身を整えることが、最も早く次の仕事に繋がる近道です。
自分を立て直す3つの実践習慣
空白期間をチャンスに変えるために、次の3つの習慣を試してみましょう。
- 朝のルーティンをつくる
同じ時間に起きて軽く散歩するだけで、脳が「安心できるリズム」を取り戻します。 - 人と話す時間を確保する
家族・友人・コーチなど、誰かに自分の気持ちを言葉にすることで、思考が整います。 - 「今日やれたこと」を1つ記録する
どんな小さなことでもOK。「洗濯できた」「外に出た」で十分です。
例:「何もできなかった日」より、「小さなことを積み重ねた日」が自信に変わる。
自分を褒めることが、再スタートの燃料になります。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事で疲れた心を回復させる方法|思考ではなく“感情”を整える

「仕事辞めたい」という感情の多くは、実は“心の疲れ”が限界に達しているサインです。
どんなに前向きに考えようとしても、頭が働かず、感情が追いつかない。
そんなときは、理屈ではなく感情の回復が必要です。
この章では、思考ではなく感情を整える3つの方法を紹介します。
「頑張る脳」が疲れきっているサイン
真面目な人ほど、「もっと頑張らなきゃ」「この仕事は自分の責任」と思い込みやすいものです。
しかし、脳のリソース(思考エネルギー)は有限。
常にフル稼働の状態が続くと、前頭前野(思考・判断)が過剰に疲労し、感情のバランスを取る扁桃体が暴走します。
例:「ちょっとしたことで涙が出る」「同僚の言葉に過敏に反応してしまう」
こうした症状は、脳が“休息を求めているサイン”です。
この状態では、ポジティブな言葉や自己啓発的な考え方は逆効果。
「頑張る」ではなく「緩める」ことが、脳の回復に直結します。
感情を整える第一歩は「認める」こと
疲れたときに最も大切なのは、“無理に変えようとしないこと”。
感情を否定すると、脳が“危険を無視している”と判断し、さらに緊張を高めます。
反対に、感情をそのまま認めるだけで、扁桃体の活動が落ち着くことが研究でわかっています。
例:「仕事に行きたくない」と思ったら、「行きたくない自分もいるんだな」と受け入れる。
「辞めたい自分」と「頑張りたい自分」が同時に存在していい。
感情を認めるときのコツ
- 「○○なのに」ではなく、「○○だからそう感じる」と言い換える
- 評価ではなく観察を意識する
- ネガティブ感情にも“理由”があると理解する
この“受容”のステップがあるだけで、仕事に対する視野が驚くほど広がります。
脳を休ませる3つの具体的回復法
感情を整えるためには、頭ではなく体を通じて脳を落ち着かせるのが効果的です。
以下の3つは、認知科学的にも“自律神経のバランス回復”に有効とされる方法です。
1. 光を浴びる
朝、自然光を浴びることでセロトニンが分泌され、脳が“安全モード”に切り替わります。
通勤前の5分でもOK。日の光を浴びながら深呼吸をしてみましょう。
2. 呼吸を整える
呼吸が浅いと、脳が“危険信号”を出し続けます。
4秒吸って、8秒で吐く呼吸法を繰り返すだけで、自律神経が整います。
3. 感情を書き出す
頭で整理しようとせず、紙に感情を書き出す。
書く行為そのものが“外在化”となり、脳内の情報を整理する効果があります。
例:「もう限界」と書くだけでも、脳は“理解された”と感じて落ち着く。
書く=自分と対話すること。これが最も簡単なセルフケアです。
「自分を満たす」時間を意図的につくる
仕事中心の生活を続けていると、「自分を満たす時間」が欠けていくことに気づきません。
しかし、心の余白をつくることは決して贅沢ではなく、エネルギー補給の習慣です。
自分を満たす小さな習慣
- カフェで一人の時間を過ごす
- 好きな音楽を流す
- 料理や散歩など、五感を使う活動をする
- 「誰かに感謝を伝える」行動を取る
例:「仕事を忘れて空を見上げる時間が、こんなに大切だったとは思わなかった」
感情を回復させるのは、特別なことではなく“日常の中の小さな快”です。
「何もしない日」を恐れない
多くの人が、休みの日に「何かしなきゃ」と焦ってしまいます。
しかし、“何もしない日”は、脳が最も深く回復する時間。
何もしていないように見えて、実は脳内では情報の統合とリセットが行われています。
例:「今日は何もできなかった」と思う日は、“次に動くための充電日”。
心が回復すれば、また自然に行動したくなる瞬間が来ます。
自分に合う仕事の見つけ方|“向いている”は探すより気づく

「仕事辞めたい」という気持ちは、決してネガティブな感情ではありません。
それは「今の仕事が、自分の本質とズレている」というサイン。
多くの人は“向いている仕事を探す”ことに意識を向けますが、本当は自分の中にすでにある“向き”に気づくことが大切です。
この章では、認知科学的な自己理解をもとに、「自分に合う仕事」を見つける方法を紹介します。
「合わない仕事」を通して、自分を知る
人は、自分に合わない環境を経験したときこそ、最も自己理解が深まります。
「辞めたい」と感じる瞬間には、必ず“自分が大切にしたいもの”が壊れているポイントが隠れています。
例:「成果ばかり求められてつらい」→「人との信頼関係を大事にしたい」
「感情を押し殺して働くのが苦しい」→「素直な自分で関われる環境を望んでいる」
つまり、仕事の違和感は「自分が何を大切にしているか」を教えてくれる信号なのです。
「辞めたい」には、“自分らしく生きたい”という前向きな意志がすでに含まれています。
「強み」は“得意”より“自然にやっていること”で見つかる
多くの人は、自分の強みを「スキル」や「実績」で判断しようとします。
しかし、認知科学的に見ると、**強みとは“無意識で繰り返している行動パターン”**です。
つまり、あなたが“頑張らなくてもできていること”こそ、本当の強みです。
強みを見つける3つの質問
- 人に褒められたとき、あなたが「たいしたことない」と思ったことは?
- 仕事で自然と引き受けている役割は?
- 夢中でやっているとき、時間を忘れているのはどんな瞬間?
例:「話を聞いていたら相手が元気になった」→共感力
「人に分かりやすく伝えるのが得意」→構造化力
「チームをまとめるのが好き」→リーダーシップ
強みとは“努力ではなく自然体で発揮される能力”。
「仕事辞めたい」と感じたときほど、自分の“自然体”を思い出すチャンスです。
自分に合う仕事は「価値観×強み×環境」で決まる
“向いている仕事”を科学的に整理すると、以下の3要素の掛け合わせで見つけられます。
| 要素 | 質問 | 例 |
|---|---|---|
| 価値観 | 何をしているときに満たされる? | 誰かの役に立つ/創造する/挑戦する |
| 強み | どんなときに自然に力を発揮できる? | 話す/整理する/提案する |
| 環境 | どんな人・空間だと安心できる? | フラットな組織/静かな環境/挑戦的な文化 |
例:「人と深く関わることが好き」「話を聞くのが得意」「落ち着いた環境が合う」
→ コーチング・教育・カウンセリングなどが向いている可能性が高い。
このように、「何ができるか」よりも「どんな状態でエネルギーが湧くか」に注目することで、無理なく続けられる仕事を見つけられます。
「仕事を選ぶ」より「生き方をデザインする」
本当に自分に合う仕事を見つけるためには、職種や業界よりも、どんな生き方をしたいかを先に決めることが大切です。
認知科学的には、脳は「目的(ゴール)」が明確なときにのみ最適な情報を探し出す性質を持っています。
つまり、あなたが「どう生きたいか」を明確にするほど、“向いている仕事”が自然に見つかるようになります。
生き方から逆算する3つの質問
- どんな1日を過ごせたら幸せ?
- どんな人に囲まれて生きたい?
- どんな瞬間に「これが自分の人生だ」と感じる?
例:「好きな人たちと笑いながら働ける」「人の変化に関わる仕事がしたい」
こうした答えの中に、“自分のキャリアの本質”が隠れています。
「向いている仕事」は、あなたの中にすでにある
「仕事辞めたい」と思うと、つい“次の正解”を探したくなります。
でも実際は、答えは外ではなく自分の中に蓄積された経験の中にあります。
過去に「嬉しかった」「やりがいを感じた」「誰かに感謝された」瞬間を思い出してみてください。
そこに共通する“感情のパターン”こそ、あなたが向いている仕事の原型です。
例:「ありがとうと言われた瞬間に喜びを感じた」→貢献型
「新しい仕組みを考えるのが楽しかった」→創造型
「人を育てるのが好きだった」→支援型
“向いている仕事”とは、外の世界で探すものではなく、自分の内側に眠っているエネルギーに気づくこと。
それに気づいた瞬間、あなたのキャリアは「辞めたい」から「選びたい」へと変わります。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
仕事を辞めたいときこそ大切にしたい人間関係の整え方|孤立しない選択

「仕事辞めたい」と思う理由の多くは、人間関係にあります。
上司・同僚・部下との関係がこじれたとき、仕事そのものよりも心が疲れてしまう。
けれど、すべての関係を断ち切る前に、“人とのつながり”の扱い方を見直すことが、次のステップを軽くする鍵になります。
「苦手な人」はあなたを映す鏡
職場で苦手な人に出会うと、「あの人さえいなければ」と思いがちです。
しかし、認知科学では、人は他者を通して自分を認識する生き物だといわれています。
つまり、苦手な相手は自分の中にある“見たくない部分”を映す鏡でもあるのです。
例:「上司の支配的な態度が嫌い」→自分の中の“従うことへの抵抗”が反応している
「無責任な同僚に腹が立つ」→自分が“責任感で縛られている”ことへの気づき
相手を変えるのではなく、「なぜ自分が反応しているのか?」を見つめると、人間関係のストレスが半減します。
これは自己理解を深める絶好の教材でもあります。
信頼できる人に“弱音”を共有する
「仕事辞めたい」と言葉にできない人は多いです。
「甘えだと思われたくない」「迷惑をかけたくない」と自分の感情を閉じ込めてしまう。
しかし、感情を抑え続けると、脳は「危険を放置している」と判断し、不安や焦りを増幅させます。
人に話す行為そのものが、**脳の情報整理(外在化)**になり、回復の第一歩となります。
例:「同僚に“正直もうしんどい”と言っただけで気持ちが軽くなった」
「友人に話してみたら、自分がどこに悩んでいるのかが見えた」
話す相手を選ぶ3つの基準
- 否定せずに聞いてくれる人
- 解決策より共感をくれる人
- 自分を尊重してくれる人
このような関係の中で話すと、「辞めたい気持ち」が整理され、「何を望んでいるのか」が浮かび上がってきます。
「支えられる側」から「支える側」にシフトする
気持ちが落ちているときこそ、誰かの役に立つ行動を取るのも効果的です。
認知科学的には、“与える行動”によって脳内にオキシトシンが分泌され、安心感と幸福感が高まることがわかっています。
これは、他人のために行動することで“自分の存在価値”を再確認できるからです。
例:「同僚の相談に乗ったら、自分も救われた気がした」
「後輩にアドバイスしていたら、自分の強みを再確認できた」
支え合う関係を持つことは、孤立を防ぎ、仕事に対する認知のバランスを取り戻します。
“仕事の人間関係”を、“人としてのつながり”に戻すことが、心を立て直す力になります。
「関係を終わらせる勇気」も時には必要
もちろん、どれだけ努力しても、改善できない関係も存在します。
その場合は、関係を終わらせることも“健康的な選択”です。
無理に合わせ続けるよりも、自分の心を守ることを優先しましょう。
例:「ずっと我慢してきたけど、距離を置いたら気持ちが穏やかになった」
「仕事を辞めて初めて、“あの環境が自分を消耗させていた”と気づいた」
人間関係をリセットするときのポイントは、「誰が悪いか」ではなく「自分をどう扱いたいか」。
これは他人を否定する行為ではなく、自分の境界線を取り戻す行為です。
あなたの心を守れるのは、あなた自身しかいません。
「孤立」と「一人になる」は違う
辞めたい気持ちが強くなると、つい「もう誰にも会いたくない」と思ってしまうこともあります。
でも、孤立=誰も理解してくれないと思い込むことであり、
一人になる=自分を整える時間を持つことは全く別です。
例:「一人で散歩したら、意外と冷静になれた」
「一人の時間があるからこそ、人との関係を大切にできた」
人とのつながりを一度手放すことは、リセットでもあり、再構築でもあります。
孤独を恐れず、“本当に心地よい関係”を選び直すことで、仕事だけでなく人生全体の質が上がります。
仕事辞めたい気持ちを“成長のサイン”に変える|脳の仕組みから見る転機の乗り越え方

「仕事辞めたい」と感じると、多くの人は「自分は弱い」「逃げている」と責めてしまいます。
でも実は、その感情こそが脳が成長の準備をしているサインです。
認知科学の観点から見ると、“辞めたい”は「変化を必要としている」という脳のメッセージ。
この章では、仕事を辞めたくなるタイミングを“成長の分岐点”として捉える方法を紹介します。
「現状維持バイアス」と「変化欲求」のせめぎ合い
人間の脳には、変化を恐れる性質(現状維持バイアス)と、成長を求める性質(変化欲求)の両方があります。
「辞めたいけど怖い」「動きたいけど動けない」という葛藤は、この2つの力が同時に働いている状態です。
例:「このままでは嫌だ」と思うのに、「今の仕事を辞めるのは不安」という二重感情。
実はどちらも“正しい反応”なのです。
認知科学的に言えば、変化の前には必ず“不快”が生まれます。
それは脳が「コンフォートゾーン(安心領域)」を超えようとしている証拠。
つまり「辞めたい」という気持ちは、“次の自分にアップデートする準備”なのです。
“辞めたい”が生まれるタイミングは、脳が新しいゴールを探しているとき
脳は目的(ゴール)があるときにだけ集中力を発揮します。
だから、今の仕事に意味を感じられなくなったとき、「辞めたい」という感情が生まれます。
それは脳が“次の目標を設定せよ”と促している状態です。
例:「この仕事に何の意味があるのかわからない」「頑張る理由が見えない」
そんなときこそ、脳は“次の道を模索中”なのです。
ゴールを再設定するには、「何をやりたいか」よりも「どうありたいか」から考えるのがポイント。
認知科学では、これを定性ゴール(Beingゴール)と呼びます。
「人に笑顔を与える自分でいたい」「挑戦を楽しめる自分でありたい」など、存在にフォーカスしたゴール設定が、脳の動機付けを再起動させます。
成長のサインを見逃さない3つのポイント
“辞めたい”をただの逃げに終わらせず、“転機”として活かすためのポイントは3つです。
1. 違和感を無視しない
違和感は、現状の延長線上に未来がないことを知らせてくれます。
見ないふりをせず、「なぜ今この感情が出ているのか?」を観察することが重要です。
2. 感情を“行動の起点”にする
「嫌だ」と感じたら、その反対にある“本当はこうしたい”を探す。
行動の出発点は、常に感情です。
3. 自分をジャッジせず、記録する
焦りや迷いが出たら、ノートに書き留めておく。
人は変化の途中で感情が乱れますが、書くことで“プロセスを見える化”できます。
例:「辞めたい」と書く日があっていい。
その言葉を見返すことで、どんな瞬間に“エネルギーが動いていたか”がわかります。
“辞めたい”は自分が進化している証拠
成長とは、過去の自分が快適に感じていた領域を超えること。
だからこそ、“辞めたい”=古い自分の価値観を手放す準備とも言えます。
例:「これまでの働き方ではもう満たされない」「もっと自分らしい仕事がしたい」
そんな思いは、成長した証であり、前に進むためのエネルギーです。
認知科学では、ゴールが更新される瞬間を「スコトーマ(心理的盲点)が外れる瞬間」と言います。
これまで見えなかった選択肢が突然見え始める。
そのきっかけこそが、「辞めたい」という感情なのです。
“仕事辞めたい”を“未来を描き直す合図”に変える
「辞めたい」という気持ちが出たときこそ、自分の人生を見つめ直すタイミング。
焦って答えを出す必要はありません。
その感情を丁寧に扱うことが、最も早い変化への道です。
未来を描き直す3ステップ
- 「今の自分は何を手放そうとしているのか?」を書き出す
- 「これからどんな自分でいたいか?」を想像する
- その未来を1ミリでも感じられる行動を今日やってみる
例:「本音で話せる人と働きたい」→同僚とランチで本音を話してみる
「人の役に立つ仕事がしたい」→誰かの相談を聞いてみる
“辞めたい”は、“次のステージへ進みたい”という内なる声。
そのサインを無視せずに受け取れば、辞めるか続けるかに関わらず、あなたの人生は確実に前進していきます。
「仕事辞めたい」から“自分の人生を生きたい”へ|本音で生きる勇気を取り戻す

「仕事辞めたい」という言葉の裏には、たった一つの願いが隠れています。
それは――「自分の人生を、自分の意思で選びたい」ということ。
辞めるかどうかは本質ではなく、あなたが“どう生きたいか”に気づくことこそが、すべての出発点です。
ここまでの章で見てきたように、「仕事辞めたい」という気持ちは、弱さでも逃げでもなく、脳と心が変化を求めているサインです。
そして、そのサインを丁寧に拾い上げていく過程こそ、自己理解の入り口。
この章では、あなたが本音で生き直すための最終ステップを整理します。
「自分を守る」から「自分を生かす」へ
多くの人が“辞めたい”と感じるとき、心の中では「もう限界だから守りたい」という反応が起きています。
でもその次の段階にあるのは、「自分を守る」ではなく「自分を生かす」という選択。
例:「この仕事に向いていない」ではなく、「私はもっとこういう働き方がしたい」。
守りの言葉を、希望の言葉に変えるだけで、現実は少しずつ動き始めます。
認知科学的に言えば、脳は“方向性を持った意図”に反応します。
だから、「辞めたい」ではなく、「こう生きたい」に焦点を当てると、RAS(脳の検索システム)が自動的に新しい選択肢を探し始めます。
人生を変える第一歩は、言葉の焦点を変えることです。
本音を取り戻す3つの問い
「仕事辞めたい」と悩んでいるとき、最も失われているのは“自分の声”です。
他人の期待・常識・世間体に囲まれていると、本音が聞こえなくなってしまいます。
そんなときに立ち返りたいのが、次の3つの問いです。
- 私はどんな瞬間に“生きている”と感じる?
- 誰と、どんな時間を過ごしているときに安心できる?
- 本当は、どんな自分でいたい?
例:「誰かの笑顔に関われたとき」「感謝を伝えられた瞬間」「安心して本音を話せる人と過ごすとき」
そこに共通して流れているのが、あなたが大切にしている“生き方のテーマ”です。
この問いは、仕事の選び方ではなく、自分の人生をどうデザインするかの問い。
本音を取り戻すとは、“自分の人生を自分のものに戻す”ということなのです。
小さな行動が、人生を動かす
変わりたいと思っても、いきなり大きな決断は必要ありません。
「辞めたい」という気持ちを行動に変えるとき、最も大切なのは小さな一歩を積み重ねることです。
行動の具体例
- 今日、自分の気持ちをノートに1行だけ書く
- 信頼できる人に「実は、最近こう思っていて…」と話してみる
- 気になる仕事・人・場所をひとつ検索してみる
例:「ノートに書いたことで、モヤモヤが整理された」
「話してみたら、“自分の思い”を初めて言葉にできた」
そんな一歩の積み重ねが、やがて“辞める勇気”や“新しい挑戦”につながります。
行動の目的は、すぐに結果を出すことではなく、自分との信頼を取り戻すこと。
「動けた自分」を積み重ねることで、自己効力感が育ち、次第に人生全体が動き出していきます。
“仕事辞めたい”は、自分を取り戻す合図
この一連の感情は、人生を見直すチャンスです。
それは“やり直し”ではなく、“再スタート”。
仕事を辞めるという選択も、続けるという選択も、どちらも正解です。
大切なのは、「どんな状態で生きていきたいか」を自分で決めること。
例:「頑張る」ではなく「心からやりたい」を選ぶ。
「周りに合わせる」ではなく「自分を大切にする」を選ぶ。
その瞬間から、あなたの人生は他の誰のものでもなくなります。
まとめ

「仕事辞めたい」という気持ちは、弱さではなく“変化を求める心のサイン”です。
焦って辞める・我慢して続けるのどちらでもなく、まずは自分の感情と本音を整理することが大切。
環境・思考・価値観を見直し、必要なら休む・話す・書き出すなどで自分を整えましょう。
向き合う過程で見えてくるのは、“辞めたい”の先にある「どう生きたいか」という本質です。
仕事は人生の一部。自分らしい生き方を選ぶ勇気こそ、これからのキャリアをつくる原動力になります
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/

透過②.png)









