自分軸で生き方は劇的に変わる!他人に流され続ける日々にサヨナラし、心から納得できる人生を歩むための実践法

「自分の人生を生きたい」と思っても、気づけば周囲に流されてしまう…。そんな経験はありませんか?それは自分軸が育っていないサインかもしれません。この記事では、心理学や認知科学の観点から「自分軸の作り方」を15のステップで解説し、すぐに実践できるヒントを紹介します。
自分軸とは何か?その基本的な意味と重要性

「自分軸」という言葉は耳にするものの、明確に説明しようとすると意外と難しいものです。シンプルに言えば、**自分軸とは“自分の価値観や信念を基準にして選択・行動する姿勢”**のことを指します。逆に、他人の意見や社会の期待を基準に動いてしまうのが「他人軸」です。
例えば、進学や就職を考えるときに「親に言われたから」「世間的に安定しているから」という理由だけで選んだ場合、それは他人軸に依存している状態です。一方で「自分は人を支えることに喜びを感じるから、この道を選ぶ」と決めるなら、それが自分軸に基づいた選択になります。
自分軸があると何が変わる?
自分軸を持つ人は、日常の判断や人間関係において迷いが少なく、エネルギーを浪費しないのが特徴です。たとえば、休日の過ごし方ひとつにしても「自分は読書でリフレッシュできる」と分かっていれば、誘いを断る罪悪感が減り、納得感のある選択ができます。
逆に自分軸が弱いと、断ることに強い不安を感じ、「嫌われたらどうしよう」と相手基準で行動してしまいます。その結果、自分のエネルギーを消耗し、**「なんとなく生きづらい」**と感じてしまうのです。
自分軸と他人軸の対比
| 項目 | 自分軸の人 | 他人軸の人 |
|---|---|---|
| 判断基準 | 自分の価値観・信念 | 他人の意見・社会の期待 |
| 感情の安定度 | 比較的安定しやすい | 流されやすく不安定 |
| 人間関係 | 対等で健全 | 過剰に合わせて疲れる |
| 成長スピード | 自分の学びに集中できる | 周囲に左右されて停滞しやすい |
このように、自分軸があるかどうかは生き方そのものを左右するのです。
認知科学的に見た「自分軸」
認知科学の観点から見ると、自分軸とは「RAS(網様体賦活系)」を通じて選択的に情報を拾う働きとも深く関係しています。自分の価値観やゴールが明確であれば、脳は自動的にその情報を優先的にキャッチし、行動をサポートしてくれるのです。
例えば「自分は人を笑顔にしたい」という価値観が強ければ、自然と人が喜ぶ瞬間に目が向きやすくなり、そこから新しいアイデアや行動が生まれます。つまり、自分軸を持つことは情報の取捨選択をクリアにし、人生をスムーズにする仕組みとも言えるのです。
実例:自分軸がある人とない人の違い
Aさん(自分軸が弱い)
友人に誘われると、特に気乗りしなくても断れず、疲れてしまう。帰宅後「またやってしまった」と後悔する。Bさん(自分軸がある)
「今日は休息を大切にしたい」と思えば、誘いを断る。友人との関係も良好で、自分も満たされている。
この違いは小さなことのように見えて、長期的には自己肯定感や人間関係の質に大きな差を生みます。
なぜ自分軸が必要なのか?現代社会の背景

今の時代、「自分軸を持つこと」は本当に大事です。昔よりも自由が増えた分、逆に迷いや不安も増えているからです。ここでは、なぜ自分軸が欠かせないのかを、現代社会の特徴から見ていきましょう。
情報が多すぎる時代
SNSやネットには毎日すごい量の情報が流れています。
- 友達のキラキラした投稿
- インフルエンサーの「これが正解!」という発信
- 広告の「買わなきゃ損」と思わせる言葉
自分軸がないと、こうした情報に振り回されてしまい、気づけば他人の人生を生きているような感覚になってしまいます。
選択肢がありすぎる時代
仕事、恋愛、趣味、副業、住む場所…。選べることが多いのは自由でいい反面、**「結局なにが正解なんだろう?」**と迷う人も多いです。
- 周囲が選んでいるから
- 親や上司に勧められたから
- なんとなく安定していそうだから
こうした理由だけで選んでしまうと、後から「これでよかったのかな?」と悩みやすくなります。
比較文化のプレッシャー
現代は「比較」が当たり前の時代です。
- 学生なら成績や偏差値
- 社会人なら年収や役職
- SNSならフォロワー数やいいねの数
数字や目に見える成果で評価されることが多いからこそ、自分の内側よりも外の基準で価値を決めてしまう人が増えています。
認知科学の視点から
脳は「自分に必要なものだけを選び取るフィルター(RAS)」を持っています。けれど、自分軸がないとそのフィルターがブレてしまい、
- 本当は必要ない情報に振り回される
- 大事なチャンスを見逃す
といったことが起こります。
具体例
例えば、就職を「親に安定した職を勧められたから」という理由だけで決めた人は、数年後に「本当にこれでよかったのかな?」と違和感を抱くことがあります。これは、自分軸が曖昧だからこそ起きる迷いです。
逆に、「人と関わるのが好きだからこの仕事を選ぶ」「自由に動ける働き方が大事」といった基準がはっきりしていれば、迷う時間が減り、納得感のある選択ができます。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸がない人の特徴とサイン

「自分軸がないかもしれない…」と思ったときに、チェックしてほしいポイントがあります。自分では意識していなくても、日常の行動や考え方にサインははっきり出ています。ここでは代表的な特徴をまとめます。
人に流されやすい
自分軸がない人は、自分の気持ちよりも相手の意見を優先してしまう傾向があります。
- 飲み会やイベントに気乗りしなくても参加してしまう
- 「嫌」と言えず、お願いを断れない
- 誰かが「こっちがいい」と言うと、すぐに考えが変わる
その場では「まぁいいか」と思えても、帰宅後に「なんで行ったんだろう」と後悔するケースが多いです。
優柔不断で決断に時間がかかる
何かを決めるときに、なかなか答えを出せないのも自分軸が弱いサインです。
- メニューを決めるのに時間がかかる
- 大きな選択ほど人に相談しないと決められない
- 「これで本当にいいのかな?」と不安になる
選択の基準が自分の中にないので、迷いが長引きやすいのです。
自己肯定感が低い
「どうせ自分なんて…」という思考にハマりやすいのも特徴です。
- 失敗すると必要以上に落ち込む
- 褒められても素直に受け取れない
- いつも周囲の評価を気にしてしまう
これは、自分の価値を自分で認められない=自分軸が弱いことの表れでもあります。
人間関係で疲れやすい
他人に合わせすぎると、当然ながら疲れます。
- 断れずにキャパオーバーになる
- 自分の感情を後回しにする
- 「なんで私ばかり…」と不満がたまる
本人は「良い人」でいようとしているのに、心の中ではモヤモヤが増えていくのです。
気持ちや行動が一貫していない
昨日は「やるぞ!」と思ったのに、今日は気分が落ちてやめてしまう。こうしたブレやすさも自分軸の弱さのサインです。自分の価値観が明確でないと、気分や周囲の影響に行動が左右されやすくなります。
具体例:Aさんのケース
Aさんは友達からの誘いを断れず、週末は予定がいっぱい。自分は疲れているのに「嫌われたらどうしよう」と思って無理に笑顔を作る。帰宅するとぐったりして、結局自分のやりたいことに時間を使えない。
Aさんのように、人に合わせることが習慣になっていると、自分の本音に気づけなくなるのです。
自分軸がないと起こる悪循環
- 判断がブレる → 迷う時間が増える
- 迷う時間が増える → エネルギーが消耗する
- エネルギーが消耗する → 自分を責めてしまう
この悪循環にハマると「なんとなく毎日がしんどい」と感じやすくなります。
まずは「気づく」ことが大切
ここまで読んで「これ自分かも…」と感じた人もいるかもしれません。でも大丈夫。自分軸がないと気づくことが、すでに自分軸を作る第一歩なんです。気づけば改善の余地が見えてきますし、行動を変えるきっかけにもなります。
「あ、私いつも断れないな」
「つい他人に合わせてしまうな」
こうした気づきは、自分軸を取り戻すサイン。ネガティブに捉える必要はありません。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸がある人の特徴とメリット

自分軸を持っている人は、一見するととてもシンプルに生きているように見えます。周囲に流されず、迷わず、自分のやりたいことに集中している。けれど、それは決して「わがまま」や「自己中心的」な態度ではありません。自分軸を持つことで、むしろ人間関係や人生がスムーズになるメリットがたくさんあるのです。
判断が早く迷わない
自分軸がある人は、普段から自分の価値観や優先順位が明確です。だからこそ、選択に迷う時間が少なくなります。
- 「これは自分にとって必要かどうか」で即判断できる
- 誘いを断るときも罪悪感を感じにくい
- 周囲に流されず、自分の納得感で決められる
結果として、決断のスピードが上がり、エネルギーの無駄遣いも減ります。
感情が安定しやすい
自分軸を持つと、他人の意見に振り回されなくなるため、気持ちの波も穏やかになりやすいです。
- 批判されても「それは相手の価値観」と受け止められる
- SNSのキラキラ投稿を見ても焦らなくなる
- 自分の基準に沿って行動しているから、満足感が得られる
感情が安定すると、対人関係でのトラブルも少なくなります。
人間関係が健全になる
自分軸がある人は「相手に合わせすぎない」ので、結果的に人間関係もラクになります。
- 自分の意見を素直に言える
- 相手との境界線(バウンダリー)を大事にできる
- お互いに尊重し合える関係を築ける
そのため、無理して合わせる関係ではなく、本当に自分を大切にしてくれる人とつながれるようになります。
成長が加速する
自分軸がある人は、自分のゴールや価値観に基づいて動くので、学びや経験がすべて「自分の軸を強める材料」になります。
- 失敗しても「これは学び」として前向きに捉えられる
- 目標が明確だから努力が続けやすい
- 自分のペースで成長できる
結果として、人生の充実感が増し、周囲からも「イキイキしている」と言われやすくなります。
具体例:Bさんのケース
Bさんは「人をサポートするのが自分の喜び」という価値観を持っています。だから、仕事もサポート系の職種を選び、日常の選択もその軸に沿っています。周囲から「もっと収入の高い職に行けば?」と言われても、Bさんは迷いません。自分の軸に合っているからこそ、今の選択に納得しているのです。
このように、自分軸がある人は「人にどう思われるか」よりも「自分がどう感じるか」を基準にしているため、日々の生活にブレが少なくなります。
自分軸があることで得られるメリットまとめ
- 判断が早く、迷わない
- 感情が安定しやすい
- 人間関係がラクになる
- 成長が加速しやすい
- 人生の納得感・満足感が高まる
つまり、自分軸を持つことは「わがまま」ではなく、むしろ周りとの関係をよりよくするための土台になるのです。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸を作る第一歩|自己理解の重要性

自分軸を作りたいと思ったとき、最初にやるべきことは自己理解を深めることです。なぜなら、自分が大切にしている価値観や、自分らしさを知らないままでは、自分軸を立てようとしてもグラグラしてしまうからです。
自己理解が浅いとどうなる?
自己理解が足りないと、自分の気持ちよりも外側の声に頼りがちになります。
- 親や友人の意見が正しいと思い込みやすい
- 「周りがやっているから」と流される
- どれが自分の本音かわからなくなる
結果的に、「あれ、自分は何をしたいんだっけ?」と迷子になり、エネルギーを失いやすくなります。
自己理解を深めるステップ
自己理解といっても、難しいことをする必要はありません。小さなことからで大丈夫です。
- 価値観を言葉にする:「大切にしたいのは自由?安心?挑戦?」
- 長所・短所を整理する:「人に合わせるのが得意=協調性」「でも断れない=課題」
- 無意識の行動パターンに気づく:「気分が落ちるとSNSを見続けてしまう」など
こうして自分の特徴を見える化することで、「あ、これが自分の軸につながるんだ」と気づけるようになります。
認知科学的な視点
認知科学では、人は「スコトーマ(心理的盲点)」によって自分の大切なことを見落とすことがあると言われています。つまり、本当は持っている価値観や才能を、自分で気づけていないことも多いのです。
例えば、友達から「あなたって人を励ますのが上手だよね」と言われても、自分では「ただ話を聞いているだけ」と思ってしまうことがあります。でもこれは立派な強みであり、自分軸を作るヒントになるポイントです。
具体例:自己理解で変わったCさん
Cさんは「やりたいことがわからない」と悩んでいました。そこで毎日10分だけ「今日楽しかったこと」をノートに書き出す習慣を始めたところ、「人と話して感謝されると嬉しい」という自分の傾向に気づきました。それからは人をサポートできる仕事に挑戦し、今では充実した日々を送っています。
このように、小さな自己理解の積み重ねが、自分軸を作る大きな一歩になるのです。
自己理解を深めるヒント
- 日記やジャーナリングで自分の感情を記録する
- 信頼できる人に「自分の強み」を聞いてみる
- 過去の成功体験や挫折から学んだことを振り返る
こうした行動はすぐに始められて、効果が実感しやすい方法です。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸を強化する「価値観リスト」の作り方

自分軸を作るうえで欠かせないのが、自分の価値観を言語化することです。価値観が曖昧なままだと、どんなに「自分らしく生きたい」と思っても、結局は他人の意見に流されてしまいます。そこで役立つのが「価値観リスト」です。
価値観リストとは?
価値観リストとは、自分が大事にしていることをキーワードや短いフレーズで書き出したものです。例えば、こんな言葉が挙げられます。
- 自由
- 安心
- 成長
- 家族
- 挑戦
- 創造
- 誠実さ
こうしたキーワードを並べていくと、「自分が何を大切にして生きているのか」が見えてきます。
リストを作るステップ
ステップ1:書き出す
思いつくままに、自分が大事にしたいと思うことを20〜30個ほど書き出します。単語でも文章でもOK。
ステップ2:グループ分けする
似た意味のものをまとめます。例えば「安心」と「安定」「居心地の良さ」は同じグループにできるかもしれません。
ステップ3:優先順位をつける
グループごとに、「どれが一番自分にとって欠かせないか」を考えます。ここで出てきた上位3〜5つが、あなたの自分軸の核になる価値観です。
具体例:価値観リストを作ったDさん
Dさんは「仕事を選ぶ基準がわからない」と悩んでいました。価値観リストを作ってみると、上位に出てきたのは「成長」「人とのつながり」「自由」。そこから「常に学びがあり、人と関われて、自分の裁量で動ける職場が合っている」と気づき、転職活動もスムーズに進みました。
このように、価値観リストは迷いを減らす“羅針盤”のような役割を果たします。
よくある落とし穴
価値観リストを作るときに注意したいのは、「人から見てよさそうな言葉」を選んでしまうことです。例えば「安定」「収入」「成功」など。もちろん大事な価値観の人もいますが、「世間的に良いから」という理由で入れてしまうと、自分軸とはズレてしまいます。
大切なのは、**「それがあると心からワクワクするか?」**という視点で選ぶことです。
リストを日常に活かす方法
- 選択に迷ったとき、「これは自分の価値観に沿っているか?」と確認する
- 新しい挑戦をする前に、価値観リストと照らし合わせる
- 定期的に見直してアップデートする
価値観は人生のステージによって変化することもあります。その時々でリストを更新していくと、自分軸がさらに強化されていきます。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸と目標設定の関係

自分軸をしっかり持つことは、目標設定とも深くつながっています。なぜなら、目標は「誰のために、何のためにやるのか」が明確でないとブレてしまうからです。ここでは、自分軸と目標の関係を整理していきましょう。
他人軸の目標は続かない
「親に安心してほしいから」「上司に評価されたいから」という理由で立てた目標は、スタートダッシュは早くても長続きしにくいです。なぜなら、動機が自分の価値観ではなく外側にあるからです。
- 受験のとき「親に言われたから頑張る」 → 合格しても達成感が薄い
- ダイエットで「人に褒められたいから頑張る」 → 褒められなくなると続かない
このように、他人軸の目標は「やらされ感」が強く、モチベーションが続きません。
自分軸に基づいた目標はエネルギーが湧く
一方で、自分軸を大事にした目標は、自然と行動に力が入ります。
- 「挑戦」が価値観なら → 新しい資格やプロジェクトにワクワクして取り組める
- 「人とのつながり」が価値観なら → コミュニティを作る目標が自然に頑張れる
- 「自由」が価値観なら → 場所や時間にとらわれない働き方を目指せる
このように、自分軸に沿った目標は「やらなきゃ」ではなく、「やりたいからやる」に変わるのです。
認知科学的な視点
認知科学では「ゴールが明確だと脳は勝手に情報を集め始める」と言われています。これはRAS(網様体賦活系)の働きによるものです。例えば「海外移住する」というゴールを決めると、普段ならスルーしていた海外関連の情報に自然と目が向くようになります。
つまり、自分軸に沿った目標を掲げることで、脳が自動的に必要な情報を拾い、行動を後押ししてくれるのです。
実例:Eさんのケース
Eさんは「もっと収入を増やさないと」という焦りから副業を始めましたが、なかなか続きませんでした。改めて価値観を整理したところ、「人を笑顔にしたい」「挑戦が好き」という軸が見えてきました。そこで副業も人を楽しませるコンテンツ作りにシフトしたところ、自然と続き、成果も出るようになりました。
Eさんのように、目標が自分軸に合っているかどうかで、結果が大きく変わるのです。
自分軸を活かした目標設定のコツ
- 目標を立てる前に「これは自分の価値観と一致しているか?」と確認する
- 数字や結果だけでなく「その過程でどんな感情を得たいか」を意識する
- 目標を人に語ってみて、ワクワク感があるかどうかをチェックする
こうした工夫をすると、表面的な目標ではなく、自分軸を反映した本質的な目標が立てられます。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸を支える「時間の使い方」

自分軸を持つためには、時間の使い方を見直すことがとても大切です。なぜなら、時間は有限であり、どこにどれだけ投資するかが「自分の軸」を形づくっていくからです。
時間を奪われていない?
自分軸が弱い人ほど、気づかないうちに「他人のための時間」が増えがちです。
- 行きたくない飲み会に参加してしまう
- 気乗りしない頼み事を引き受けてしまう
- SNSをだらだら見て、気づけば数時間経っている
こうした行動は「他人軸」で動いているサイン。時間をどう使うかは、そのまま自分軸の強さに直結します。
自分軸のある人の時間の特徴
自分軸を持っている人は、時間の使い方に一貫性があります。
- 大切な価値観に沿ったことに時間を使う
- 不要な誘いや依頼をきっぱり断れる
- 自分のエネルギーを「やりたいこと」に注げる
だからこそ、同じ24時間でも満足感がまったく違うのです。
認知科学的な視点
脳は「繰り返すこと」に強く影響されます。毎日の時間の使い方は、そのまま脳に「これが大事なんだ」と刷り込む行為です。例えば、毎日SNSに2時間費やしていると、脳は「SNSが自分にとって重要」と認識し、さらにそちらに注意を向けやすくなります。
逆に、自分軸に沿った行動(学び・運動・人との本質的な交流など)に時間をかければ、脳はその価値観をさらに強化してくれます。
具体例:Fさんのケース
Fさんは「本を読みたい」と思いながら、毎晩スマホでSNSを見てしまう習慣がありました。そこで、寝る前の30分だけスマホを別の部屋に置き、本を読むことにしました。最初は違和感があったものの、1か月後には「この時間がないと落ち着かない」と感じるようになり、自分の価値観である「学び」を日常に定着させることができました。
このように、小さな時間の選び方が、自分軸を支える基盤になるのです。
時間の使い方を変えるコツ
- 1日のスケジュールを振り返り、「これは本当に必要だったか?」をチェックする
- やらなくてもいいこと(ムダなSNS、義務感だけの予定)を削る
- 自分の価値観に直結する行動を優先的にカレンダーに入れる
こうした工夫をするだけで、時間の流れが「他人に奪われるもの」から「自分で選ぶもの」へと変わっていきます。
時間の選び方=自分軸の強さ
結局のところ、時間は人生そのものです。自分の時間をどう選ぶかが、自分軸をどれだけ大事にできているかの指標になります。だからこそ、自分軸を作りたいなら、まずは「時間の使い方」を整えることから始めてみましょう。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸を崩す「よくある落とし穴」

せっかく自分軸を意識していても、気づかないうちに崩れてしまうことがあります。その原因は、日常の中に潜んでいる“落とし穴”。ここでは、多くの人がハマりがちなパターンを紹介します。
完璧主義
「自分はこうしたい!」という想いがあっても、完璧にやろうとしすぎると逆に自分軸が揺らぎます。
- 100点を目指して行動が止まる
- 少しのミスで「やっぱり自分はダメだ」と思う
- 人と比べて焦ってしまう
完璧主義は「自分の基準」ではなく「他人からどう見られるか」が軸になりがち。結果的に、行動よりも評価を優先してしまうのです。
周囲の期待に合わせすぎる
家族や友人、職場の人からの期待に応えようと頑張りすぎると、自分の気持ちより相手の気持ちを優先してしまう状態になります。
- 本当は転職したいのに「親が心配するから」と現状維持
- やりたくない仕事も「上司に頼まれたから」と断れない
- 趣味やプライベートを削ってまで他人に尽くす
もちろん相手を大切にすること自体は悪くありません。ただし、自分の心を置き去りにすると「他人軸」に傾き、自分軸が弱まってしまいます。
比較癖
現代はSNSの普及もあって、他人との比較が習慣化しやすい時代です。
- 「あの人はもう結婚しているのに、自分はまだ…」
- 「同年代なのに収入が違いすぎる」
- 「フォロワー数で差をつけられている」
こうした比較は、自分軸ではなく「外の基準」で自分を測る行為。やればやるほど、自分の価値が見えにくくなります。
便利さに流される
現代は便利なサービスや誘惑があふれています。動画配信、SNS、オンラインショッピング…。気づけば何時間もスマホを見てしまうことも少なくありません。便利さに流されると、本来やりたかったことや大事にしたい価値観が後回しになり、自分軸がぼやけてしまいます。
具体例:Gさんのケース
Gさんは「自分の時間を大切にしたい」と思っていましたが、仕事帰りは疲れて毎日スマホで動画を見続けていました。最初はリフレッシュのつもりでも、気づけば寝る時間を削り、翌日はさらに疲れる…。本来大事にしたい「健康」や「自己成長」が後回しになっていたのです。
このように、ちょっとした習慣や考え方のクセが、自分軸を崩す落とし穴になりやすいのです。
落とし穴にハマらないために
- 「これって本当に自分のため?」と自問する習慣をつける
- 比較したくなったら、SNSから一度離れる
- 完璧を目指すより「まず一歩やってみる」を意識する
小さな心がけが、自分軸を守る大きな力になります。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸と人間関係のバランス

「自分軸を持つ」と聞くと、「周囲に合わせずに自分勝手に生きること」と誤解されることがあります。でも、実際はそうではありません。自分軸と人間関係は対立するものではなく、むしろ両立させることでより良い関係を築けるのです。ここでは、自分軸と人との関わりをどうバランスさせるかを見ていきましょう。
自分軸=わがままではない
自分軸を大事にしている人は、他人の意見を無視しているわけではありません。
- 自分の価値観に沿って行動する
- 相手を尊重しつつ、自分も大切にする
- 無理な妥協をしない
つまり「自分も大事に、相手も大事に」という姿勢。これは本当の意味での健全な人間関係につながります。
バウンダリー(境界線)の考え方
人間関係で自分軸を守るために欠かせないのが、**境界線(バウンダリー)**です。
- 自分の責任と相手の責任を区別する
- 相手の感情をすべて背負い込まない
- 「ここからは自分の領域」という線を引く
例えば、友人が落ち込んでいるときに寄り添うことは大切です。でも「相手が元気になるまで全部面倒を見なきゃ」と思ってしまうと、自分が疲弊してしまいます。バウンダリーを意識することで、自分を守りつつ相手を大事にできるのです。
自分軸が人間関係をラクにする理由
自分軸があると、人間関係のストレスはぐっと減ります。
- 無理に合わせなくなる → 本当に合う人と関係が深まる
- 断るときも「罪悪感」より「納得感」が強くなる
- 自分を理解しているから、相手の違いも受け入れやすい
結果的に、関わりの質が高まり、「この人とは一緒にいて楽しい」と思える関係が自然に増えていきます。
具体例:Hさんのケース
Hさんは以前、友人の誘いを断れず、毎週末予定を詰め込んでいました。けれど自分軸を意識するようになり、「週末は自分の時間を大切にする」と決めたところ、無理に参加することが減りました。不思議なことに、友人からの信頼も失われず、むしろ「Hさんって自分を大事にしてて素敵」と言われることが増えたのです。
このように、自分軸を持って行動すると「嫌われるかも」という不安は実際には少なく、むしろ人間関係がラクになるケースが多いのです。
バランスを取るための工夫
- 相手の意見を聞いたうえで、自分の考えも伝える
- 誘いを断るときは「NO」+「別の提案」で柔らかく返す
- 感情的に反応する前に「自分はどうしたい?」と立ち止まる
こうした工夫を積み重ねることで、相手との関係を壊さずに自分軸を守ることができます。
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸を作るための習慣化テクニック
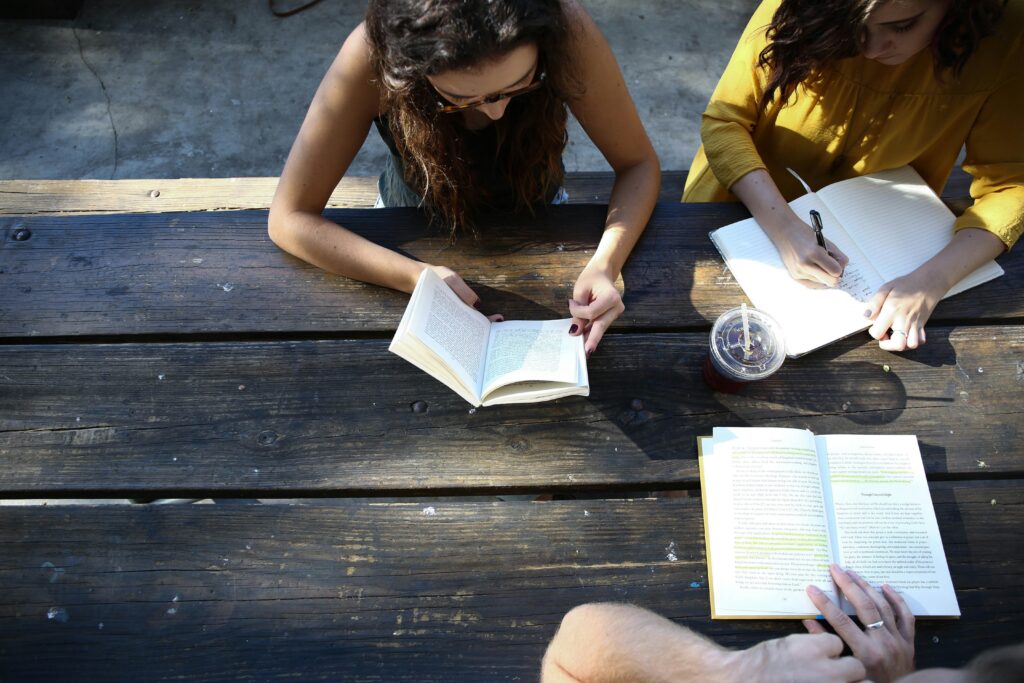
自分軸は一度作れば終わりではなく、日々の習慣を通じて少しずつ育てていくものです。習慣は無意識のレベルで自分を形づくる力があるため、続けるだけで「自然と自分軸が強くなる」仕組みを作れます。ここでは実践しやすい習慣化の方法を紹介します。
朝のルーティンを整える
朝の時間は一日の方向性を決める大事なタイミング。
- 5分だけでも瞑想をする
- ノートに「今日やりたいこと」を3つ書く
- 軽い運動で体を目覚めさせる
これを習慣にすると、「今日は自分で一日を選んでスタートした」という感覚が強まり、自分軸のスイッチを入れる効果があります。
ジャーナリング(書く習慣)
「頭の中で考えていること」をノートに書き出す習慣は、自己理解を深めるうえで非常に有効です。
- 感情を書き出すと、自分が本当に大切にしていることが見える
- 悩みを書き出すと、「これは他人軸だったな」と気づける
- 書くことで頭が整理され、判断がしやすくなる
たとえば「今日嬉しかったこと」「今日イラッとしたこと」を毎晩3行だけでも書いてみると、自分の傾向が浮き彫りになります。
瞑想・マインドフルネス
自分軸を作るうえで「今この瞬間に集中する力」は欠かせません。瞑想やマインドフルネスを習慣化すると、
- 周囲の情報に振り回されにくくなる
- 自分の感情を客観的に見られる
- 不安や迷いに流されず、自分の基準に立ち戻れる
認知科学的にも、マインドフルネスは脳の前頭前野を活性化させ、意思決定力を高める効果があるとされています。
小さな「自分優先」を積み重ねる
自分軸は、小さな選択の積み重ねで強くなっていきます。
- 行きたくない飲み会は断る
- 疲れているときは無理せず休む
- やりたいことを1日5分でもやってみる
こうした小さな「自分を優先する行動」が、長期的に大きな違いを生みます。
具体例:Iさんのケース
Iさんは「人に流されやすい」と悩んでいました。そこで毎朝5分だけ「今日やりたいこと」を書き出す習慣を始めたところ、1週間ほどで「今日はこれをやる!」と意識して動けるようになりました。周囲の誘いに対しても「今日は予定があるから」と言えるようになり、自分軸が少しずつ強まっている実感を得られました。
習慣化のコツ
- 最初から完璧を目指さない(1日5分でOK)
- トリガーを決める(朝の歯磨き後にノートを書く、など)
- 続けられたら自分をしっかり褒める
習慣は「量より継続」。無理のない範囲でコツコツ続けることで、気づけば自分軸が自然と根付いていきます。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸と「感情コントロール」の関係

自分軸を持つことと、感情をうまくコントロールすることは切っても切れない関係があります。なぜなら、感情に振り回されると、自分軸ではなく他人軸で動いてしまいやすいからです。ここでは、自分軸と感情の関係について掘り下げていきます。
感情に流されると起こること
- ちょっとした言葉にイライラして反応してしまう
- 周囲の雰囲気に合わせて無理に笑顔を作る
- 不安や焦りに駆られて、やりたくないことを選んでしまう
こうした行動は一見「仕方ないこと」のように思えますが、実際は感情が主導権を握り、自分軸が機能していない状態です。
自分軸があると感情を客観視できる
自分軸を持つ人は、「自分は何を大切にしたいのか」が明確です。そのため、感情に反応しそうになったときでも、一呼吸おいて冷静に対処できます。
- 批判的な言葉を受けても「相手の価値観に基づいた意見だな」と受け止められる
- 不安になっても「自分はこうしたい」と基準に立ち戻れる
- 喜びやワクワクも、自分の軸に沿って増幅できる
つまり、自分軸は「感情に流されずにハンドルを握り続ける力」になるのです。
認知科学的な仕組み
認知科学では、人の行動は「感情→思考→行動」という流れで決まることが多いとされます。しかし、自分軸が明確な人は「価値観やゴール」が先にあるため、感情が暴走してもそれを修正するフィルターが働きます。
具体的には、RAS(網様体賦活系)が「自分に必要な情報だけを拾う」働きをするので、不安や怒りよりも「目標達成につながる情報」を意識しやすくなるのです。
感情コントロールの実践方法
1. 感情を言葉にする
「今、イライラしている」「不安を感じている」と言語化すると、感情を客観的に見ることができます。
2. 一時停止の習慣
感情的になったときは、その場で反応せずに深呼吸。数秒待つだけで、自分軸に立ち戻りやすくなります。
3. ポジティブな習慣で整える
運動・睡眠・食事など、身体を整えることも感情の安定に直結します。体調が整うと感情の振れ幅も小さくなるのです。
具体例:Jさんのケース
Jさんは職場で上司に厳しく指摘されると、すぐに落ち込み「自分はダメだ」と思っていました。しかし、ノートに感情を書き出す習慣を始めてから、「落ち込んでいるけど、それは上司の基準。自分は成長したいから改善してみよう」と考えられるようになりました。結果として、感情に振り回されず行動できるようになり、評価も上がっていきました。
感情と自分軸は支え合う
感情を上手に扱えるようになると、自分軸がブレにくくなります。そして、自分軸を強めるほど、感情のコントロールも楽になります。両方はお互いを支え合う関係にあるのです。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
自分軸を強めるための失敗経験の活かし方

多くの人が「失敗=避けたいもの」と考えがちですが、実は失敗は自分軸を強める最高の材料になります。なぜなら、失敗を通じて「自分にとって本当に大切なもの」が浮かび上がるからです。
失敗が教えてくれること
失敗はただの「マイナス」ではなく、学びの宝庫です。
- どんな選択をしたときに後悔したのか
- なぜモチベーションが続かなかったのか
- 何を優先した結果うまくいかなかったのか
これを振り返ると、「自分はこういうことを大事にしているんだ」と、自分軸のヒントが見えてきます。
他人軸での失敗は特に学びが大きい
人に合わせて決めた選択がうまくいかなかったとき、強烈な違和感を感じることがあります。
- 親に言われた進路に進んだ → 楽しくない
- 友達に勧められた趣味を始めた → 続かない
- 上司の期待で動いた → ストレスばかり
こうした「他人軸での失敗」は、自分軸を見つけるきっかけになります。逆に言えば、失敗しないと自分の本当の気持ちに気づけないことも多いのです。
認知科学的な視点
認知科学では「失敗は脳の学習プロセスに不可欠」とされています。脳は「エラー」を検知することで新しい神経回路を作り出し、次の行動に活かします。つまり、失敗は自分軸を修正・強化するための重要なデータなのです。
具体例:Kさんのケース
Kさんは「安定しているから」という理由で大手企業に就職しました。しかし数年働くうちに「やりがいを感じない」「毎日が苦しい」と思うように。転職を考える中で、「自分は挑戦と成長を求めている」と気づき、スタートアップへ転職。結果的に、毎日が充実し、自分軸がはっきりしました。
このように、失敗を経験したからこそ、自分軸が明確になった例は数多くあります。
失敗を活かすための振り返り方法
失敗をただ「ダメだった」と片付けるのではなく、以下のように振り返ると学びに変わります。
- そのとき自分はどんな選択をしたか?
- その選択は誰の基準に沿っていたか?(自分?他人?)
- 失敗を通じて「本当に大事だと思ったこと」は何か?
このプロセスを繰り返すことで、失敗が「自分軸を強くするデータベース」になっていきます。
失敗を恐れないために
- 失敗は「自分軸を見直すチャンス」と捉える
- 他人に笑われても「学びを得た」と思えばOK
- 小さな挑戦を繰り返し、失敗の耐性をつける
失敗を恐れず積み重ねていくと、自分軸はどんどん太く強くなっていきます。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
他人の意見を参考にしつつ自分軸を保つ方法

自分軸を持つことは大切ですが、だからといって「他人の意見を一切聞かない」のは逆効果です。むしろ、他人の意見は自分の視野を広げる貴重な材料になります。ただし、それをそのまま鵜呑みにしてしまうと自分軸が揺らぎやすいので、上手な取り入れ方がポイントです。
他人の意見が役立つ場面
- 自分では気づかなかった強みを指摘してもらえたとき
- 新しい選択肢や方法を知れるとき
- 客観的なアドバイスで視野が広がるとき
このように、他人の意見は「気づきのきっかけ」になります。特に信頼できる人からの言葉は、自分軸を磨くヒントになることも多いです。
他人の意見に振り回されるときの特徴
一方で、自分軸が弱いときは意見をそのまま取り入れてしまいがちです。
- 「あの人が言うなら間違いない」と信じすぎる
- 断れずにそのまま実行してしまう
- 反対されるとすぐに不安になる
この状態は、意見を参考にするのではなく、依存してしまっているサインです。
自分軸を保つための工夫
1. 意見を「材料」として受け取る
他人の意見は正解ではなく、あくまで「その人の価値観に基づいた視点」だと考えるとラクになります。
2. 自分の価値観と照らし合わせる
聞いた意見をそのまま採用せず、「これは自分の価値観と合っているか?」と確認することが大切です。
3. 一度寝かせてから判断する
すぐに決めるのではなく、1日置いて考えると自分の本音が見えやすくなります。
具体例:Lさんのケース
Lさんは「安定した仕事がいい」と家族から勧められ、公務員を目指していました。けれど勉強するうちに「人と関わりながら自由に働きたい」という自分の気持ちに気づきました。最終的に公務員ではなく、教育関係の仕事に就職。家族の意見は参考にしつつも、自分軸を大切にしたことで納得のいく選択ができたのです。
情報社会での意見の取捨選択
今はSNSやネットで、無数の意見や価値観に触れられる時代です。だからこそ、
- すべてを信じ込まず「これは誰の価値観?」と考える
- 複数の意見を比べて、自分に合うものを選ぶ
- 情報の洪水に流されないよう、意識的に距離をとる
こうした姿勢が、自分軸を守るうえで欠かせません。
自分軸を守りながら他人の意見を活かすと…
- 必要なヒントだけを取り入れられる
- 他人の価値観に学びつつ、自分の成長に変えられる
- 「意見は意見、自分は自分」と分けて考えられる
結果的に、人の意見を参考にしつつも、自分らしい選択ができるようになるのです。
自分軸を作り続けるために必要な「伴走者」

ここまで読んで「よし、自分軸を作ろう!」と思った人もいるかもしれません。でも実際には、一人で取り組んでいると途中で迷子になったり、挫折してしまうことも少なくありません。なぜなら、自分の無意識のクセや思い込みには自分では気づきにくいからです。そんなときに力になってくれるのが「伴走者」の存在です。
伴走者がいることで得られるメリット
- 第三者の視点で、自分の思考や行動パターンを見てもらえる
- 本当は避けていた課題に気づかせてもらえる
- 迷ったときに「自分軸に沿っているか」を一緒に確認できる
伴走者は答えを押し付ける人ではなく、自分が自分の答えに気づくようサポートしてくれる存在です。
一人だと気づけない無意識のパターン
認知科学の観点から見ると、人は誰しも「スコトーマ(心理的盲点)」を持っています。これは、見えているのに認識できない情報のこと。例えば、
- 本当は「やりたくない」と思っているのに、無意識に我慢している
- 自分では「ただの弱点」と思っていたことが、実は大きな強みだった
- 「当たり前」だと思っている考え方が、自分軸を狭めていた
こうした盲点は、自分ひとりではなかなか発見できません。伴走者がいることで、見えていなかった本当の自分に気づけるのです。
具体例:Mさんのケース
Mさんは「何をやっても中途半端」と悩んでいました。しかし、コーチとの対話を通じて「自分は人を楽しませることに自然とエネルギーを注いでいる」と気づきました。そこから「楽しませる」を自分軸に据えた結果、仕事でもプライベートでも主体的に動けるようになったのです。
Mさんのように、伴走者がいることで「自分では見えなかった自分軸」が見つかりやすくなります。
どんな伴走者を選べばいい?
- 否定せずに話を受け止めてくれる人
- アドバイスより「問いかけ」で気づきを促してくれる人
- 自分の成長を一緒に喜んでくれる人
友人や家族でもいいですが、客観性を持ってサポートしてくれる存在として、コーチングやカウンセリングを利用するのもおすすめです。
「なないろ・コーチング」の役割
「なないろ・コーチング」では、認知科学をベースにした対話を通じて、あなたの無意識のパターンを整理し、自分軸を見つけて強化するサポートをしています。
- 自分の価値観を明確にする
- 無意識の思考パターンを知るための問いかけ
- 日常に落とし込むための具体的アクション
こうしたプロセスを一緒に進めることで、「一人では気づけなかった自分軸」が自然と浮かび上がってくるのです。
自分軸は「育て続けるもの」
最後に大事なのは、自分軸は一度作れば終わりではないということです。人生のステージや環境が変われば、価値観もアップデートされます。だからこそ、定期的に見直し、伴走者と一緒に育て続けることが必要なのです。
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
まとめ

「自分軸を作る」というのは、単なる自己啓発の流行語ではなく、人生を迷わず生きるための基盤です。現代社会は情報も選択肢も多く、他人の価値観に流されやすい環境だからこそ、自分の価値観を言語化し、日々の行動に落とし込むことが大切です。自己理解、価値観リスト、時間の使い方、感情コントロール──どれも小さな積み重ねが「自分らしさ」を強めてくれます。そして一人では気づけない無意識のパターンも、伴走者の存在があれば発見しやすくなります。今の自分を見直し、自分軸を育てる一歩を踏み出してみませんか?
\まずは体験からはじめてみませんか?/
リベルテでは、認知科学に基づいた1対1の体験コーチングをオンラインで受けられます。
「自分の強みが見えない」「今のままでいいのか不安」「やりたいことが見つからない」――
そんな迷いも、深い対話を通じて“あなた自身の答え”が浮かび上がってきます。
安心できる場で、自分の可能性を一緒に掘り起こしてみませんか?
\ リベルテでありのままで生きられる明日を!/
透過②.png)









